今回は、会社法で規定された取締役会および取締役の制度について解説する。会社法では「取締役会の決議の省略」、「取締役会への報告の省略」、「特別取締役による取締役会の決議」など、新たな制度が導入されている。以下で、重要な部分を中心に紹介しよう。
取締役会とは、取締役全員で構成し、業務執行に関する会社の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する機関である。
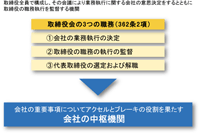 ▲図1 取締役会とは [画像のクリックで拡大表示] |
会社法362条2項によれば、取締役会の職務は大きく分けて3つある(図1)。(1)会社の業務執行の決定、(2)取締役の職務の執行の監督、(3)代表取締役の選定および解職である。要するに、会社の重要事項についてアクセルとブレーキの役割を果たす会社の中枢機関である。大企業においては、取締役会を重要事項の決定機関ととらえた上で、実質的な議論はその下部組織の経営会議で行うことも多い。
会社法では、重要な財産の処分や譲り受け、多額の借財、大会社における内部統制システムの整備など、重要な業務執行の決定については、取締役に委任することができない、としている。こうすることで、取締役会の業務執行の範囲を定める一方で、日常的事項に関する決定は代表取締役などに委譲できることを明らかにしている。実務上は、取締役会での決定事項や報告事項は、会社法を踏まえつつ、より詳細に記載した取締役会規程に基づいて運営されるのが通常である。
迅速な意思決定のための書面決議
改正前の商法では、取締役会決議は必ず、実際に取締役会を開催したうえで決議をしなければならない、とされていた。書面による決議や持ち回り決議は認められず、そのように判示する判例も存在していた。
これに対し会社法では、迅速な意思決定が求められる最近の経営環境に対応し、定款で定めれば、下記の場合に取締役会の開催を省略できるようにした(370条)。すなわち、議決に加わることができる取締役全員が、書面(または電子メールなど)によって議案に同意する意思表示をした場合には、その提案を可決した取締役会決議があったものとみなすこととした(ただし、監査役が不可を述べた場合は、取締役会の開催が必要)。
この制度は、会社法による法改正のうち最も導入が進んでいる制度の1つである。5月1日の会社法施行以降、多くの会社が定款変更議案として提案し、株主総会決議を経て導入している。
また、取締役会への報告事項についても、取締役・監査役の全員に通知した場合には、取締役会への報告は省略できることとした(372条)。もっとも、363条2項による3カ月ごとの報告は必ず必要なので、取締役会は最低でも3カ月に1度は開催されることになる。
このように手続きの省略化を認める一方、会社法では議事録の記載事項を詳細に定めるなど、経営の健全化のために一定の措置を施している。すなわち、旧商法においては、議事の経過および要領を記載するとの規定(旧商法260条の4)しか存在しなかったのに対し、会社法では、取締役会議事録に記載すべき事項を詳細に規定している(369条3項、会社法施行規則101条3項)。
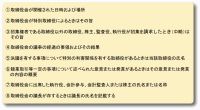 ▲図2 会社法で詳細に規定している 、取締役会議事録に記載すべき事項 [画像のクリックで拡大表示] |
具体的には、(1)取締役会が開催された日時および場所、(2)取締役会が特別取締役によるときはその旨、(3)招集権者である取締役以外の取締役、株主、監査役、執行役が招集を請求したとき(中略)はその旨、(4)議事の経過の要領およびその結果、(5)決議を有する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは当該取締役の氏名、など8項目である(図2)。
このほか、旧商法においても、テレビ会議や電話会議による取締役会が解釈により認められてきたが、会社法では「当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人または株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法」が取締役会議事録の記載事項に含まれており、テレビ会議や電話会議によって取締役会が実施されることを想定している(施行規則101条3項1号)。
ここまで見てきたように、会社法では、書面による持ち回りやテレビ会議方式・電話会議方式を認めるなど、迅速な意思決定のための柔軟な意思決定を可能としている。その一方で、取締役会議事録の記載事項の充実化を図り、コーポレートガバナンスの観点から一定の歯止めをかけているのである。
取締役はリスク管理体制構築の義務を負う
取締役の職務は、取締役会の構成員として業務執行の意思決定に参加することと、代表取締役をはじめとする取締役の行為が法令・定款に遵守していることを監視することである。
旧商法では判例により、取締役は取締役会の構成員として、リスク管理体制を構築する義務を負い、さらに、代表取締役と業務執行取締役がリスク管理体制を構築する義務を履行しているかどうかを監視する義務を負う、とされてきた(大和銀行事件 大阪地裁平成12年9月20日など)。この義務は引き続き、会社法においても効力を有する。前回の連載(「法務から理解する内部統制」)でも繰り返し説明した通り、会社法では大会社の取締役会に内部統制システムの構築義務が課されているが、個々の取締役にとってもリスク管理体制の構築は重要な責務なのである。
ガバナンス強化のため普通決議による解任を可能に
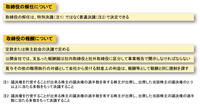 ▲図3 取締役の「解任」と「報酬」に関する規定 [画像のクリックで拡大表示] |
取締役に関する重要な改正点として、取締役を解任するための要件が、株主総会での「特別決議」から「普通決議」へ緩和されたことが挙げられる。特別決議とは「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議すること」、普通決議とは「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数に当たる多数をもって決議すること」である。
このように取締役解任の要件が、「3分の2以上」から「過半数」へ緩和された理由について、立法担当者は次のように説明している。(1)昨今、株主総会による取締役会の選解任を通じて取締役をコントロールし、株式会社のガバナンスの向上を図るべきであるという指摘が強まっていること、(2)会社法においては、株主総会決議を必要としない組織再編行為の範囲を拡大するなど、会社経営の機動性や自由度を高める措置を講じており、株主の意向を会社経営に反映させるための手段としての株主総会による選解任の重要性が増していること。
株主総会の普通決議は、計算書類の承認など、定時総会で定期的に承認を受ける議案の要件とされるもので、株主総会による承認手続きの要件としては最も“軽い”ものである。このような普通決議で、取締役の解任という重要な手続きを可能にしたことは、それだけ会社法がコーポレートガバナンスを重視していることを強く示すものといえよう。
取締役の報酬額は定款や株主総会で決定
会社法では、取締役が受け取る報酬の額を、定款または株主総会の決議で定めることを要求している(361条)。報酬額の決定を取締役会に委ねると、同僚意識から制御がきかなくなる恐れがあるからだ。
公開会社は取締役に支払った報酬額を、「社内取締役」と「社外取締役」に区分して事業報告で開示しなければならない(会社法施行規則121条4号、124条6号)。このように会社法は、コーポレートガバナンスの観点から情報開示を求めている。
取締役の「報酬」には、現金以外のストックオプションや株式などの現物報酬も含まれる。また、従来は慣行で“利益処分”として処理されてきた取締役の賞与についても、会社法では「賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益」(361条1項)は「報酬等」として全て報酬と同じ規制を課すこととした。実務上は、株主総会の決議で報酬や賞与の支給基準を示し、具体的な金額・支払期日・支払方法などはその基準に基づいて取締役会が決定する、といった方法が多くとられている。
次に、コーポレートガバナンスの象徴的存在である「社外取締役」について説明しておこう。 社外取締役とは、「(1)株式会社の取締役であって、(2)当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、(3)過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがない者」をいう(2条15号)。委員会設置会社については、委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(400条3項)、社外取締役のみ責任限定契約を会社と締結できる(427条)、といった規定がある。
会社法および会社法施行規則では、社外取締役の活動状況が、公開会社の事業報告の記載事項となっており(435条2項、施行規則124条)、活動状況の一つとして取締役会における発言の状況が掲げられている。このように会社法では、株主に対して社外取締役に関する情報開示を進めている。
2002年(平成14年)に旧商法下で導入された社外取締役制度は、最近になって多くの企業に導入されており、会社法でも同制度の導入をより進めている。敵対的買収において社外取締役が主体的な役割を果たすことで、取締役会の決議の信頼性が高まるなど、社外取締役の新しい役割が注目されている。
取締役会と内部統制システム構築
前回の連載「法務から理解する内部統制」の第4回と第5回において、会社法で規定された、取締役会で決議すべき内部統制システムについて解説した。その後、立法担当者による著作「論点解説 新・会社法 千問の道標」(商事法務)が刊行され、会社法における内部統制システムについて以下のような考え方が示された。ここでは、特に重要と思われる部分を要約して指摘しておく。
|
・米国のCOSOレポート(COSOの説明はこちら)と会社法上の内部統制システム(362条4項)とは、直接の関係はない。例えば、これまで内部統制システムと呼ばれてきたものは、業務執行機関内における内部統制システムであり、会社法における内部統制システムは「業務執行機関の外部の機関である監査役」による業務執行機関の統制を含む点で大きく異なる。 ・会社法では内部統制の考え方を一歩押し進めて、監査役をそのシスムに組み込むとともに、取締役会の定めた内部統制システム自体を監査の対象とする。そして、その内容が相当でないと監査役が認めるときは、その旨およびその理由を監査報告に記載することとする(施行規則129条)。このように、会社のすべての機関を活用して、株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の構築を目指すところに、その特徴があると言える。 ・会社法362条4項などでは、内部統制の「体制そのもの」ではなく「体制の整備」について、取締役会で決議して定めなければならないとしているから、「内部統制システムを設けない」という決定をしても362条4項などには違反しない。ただし、取締役が会社の性質や規模に応じた内部統制システムを整備していない場合には、別途、善管注意義務(330条)違反として任務懈怠責任(423条1項)を問われる可能性がある。 ・取締役が362条4項6号に掲げる事項について決議した場合には、その内容のいかんにかかわらず、同号に違反することはない。ただし、当該会社の規模や業務内容に応じて、株式会社の業務の適正を確保するために不十分なものであった場合には、その体制の決定に関与した取締役は、善管注意義務に基づく任務懈怠責任を問われうる。 ・決定した内部統制システムは適切なものであったが、その内部統制システムが実際には遵守されず、取締役がそれを長期間放置している場合にも、取締役は、善管注意義務に基づく任務懈怠責任を問われる可能性がある。 ・取締役会の決議すべき事項は「体制の整備」であるから、例えば監査役の補助者の人数や人選などの個々の決定については、必ずしも取締役会で行う必要はない。目標の設定、目標達成のために必要な内部組織、およびその権限、内部組織間の連絡方法、是正すべき事実が生じた場合の是正方法などに関する重要な事項(要項・大綱)を決定すれば足りる。 ・内部統制システムの整備については、取締役会で一度決定すれば、その決定を取り消されない限り、362条4項などには反しない。ただし、会社の実情の変化により、当初、適切であった内部統制システムが十分に機能しなくなったにもかかわらず、これを放置し続ければ、取締役が善管注意義務違反に問われる可能性があるので、そのような場合には、取締役会において新たな内部統制の整備を決定すべきである。 |
(次回へ)
|





















































