まず、日本において取締役の商法上の責任がどのように問われてきたかについて概観しておく。
旧商法においても取締役の責任が問題となった事案は多く、取締役の様々な違法行為が問題とされてきたが、その内容は時代とともに変化してきた。すなわち、旧商法の基本的な枠組みが制定された1950年(昭和25年)から1980年代後半までは、取締役の親族に対する金銭などの便宜供与や総会屋に対する利益供与などの事案が多かった。これらは、常識的に考えれば社会的相当性を欠くものであることが多く、裁判所も比較的判断がしやすかったのではないかと推測される。
ところがバブル崩壊後、バブル期に行われた銀行・証券会社などの損失補填やインサイダー取引、取引先への巨額融資の焦げ付きなどが問題となるにつれ、取引が複雑で経済的な知識が要求される事案が急増した。こうした状況を背景に、日本の裁判所は米国におけるビジネス・ジャッジメントルール、いわゆる「経営判断原則」を導入した(野村證券事件、1993年9月16日付東京地裁判決)。
経営判断原則とは、「具体的な法令に違反しない場合の企業の経営判断については、不確実かつ流動的な,さまざまな要素を対象とした専門的な判断が要求されるので、基本的にはその判断を尊重するべきである。その上で、 (1)前提となった事実の認識について不注意な誤りがなかったかどうか、また、(2)その事実に基づく意思決定の過程が通常の企業人として著しく不合理でなかったかどうか、といった観点から判断するべきである」とする考え方である。
このような経営判断原則が判例上、採用された後も、取締役の責任が問われた事案は多く存在するが、近年の特徴としては取締役の内部統制構築義務(リスク管理体制の構築義務)を認めた上で、その点に不備があったことが問題となる事例が増加している点が挙げられる。例えば、金融機関の海外支店の行員による巨額損失を防止できなかったとして、取締役十数名に総額829億円もの賠償義務を認めた大和銀行事件大阪地裁判決(大阪地裁2000年(平成12年)9月20日)をはじめ、ヤクルト株主代表訴訟事件判決 (東京地裁2001年(平成13年)1月18日)、ダスキン株主代表訴訟事件判決(大阪地裁2004年(平成16年)12月22日)、雪印食品株主代表訴訟事件判決(名古屋高裁金沢支部2005年(平成17年)5月18日、原審の判決は金沢地裁2003年(平成15年)10月6日)などがある。
これらはいずれも、虚偽表示や不正行為を発見できなかった取締役の責任が問題となり、リスク管理体制を構築していたかどうかという点が争われた事案である(詳細は、本サイトで筆者が以前連載した「法務から理解する内部統制」の「第3回 判例から見る日本の内部統制」を参考にされたい)。
以上のように、取締役の責任が問われた事例は時代により変化しているが、会社法においては、旧商法における基本的な枠組みを維持しつつも、旧商法の度重なる改正によって生じた制度の不整合をなくす、解釈が分かれていた部分を明確にする、といった視点から修正を加えている。以下で、特に重要な点について解説していこう。
(1)制度の不整合を回避

▲図1 取締役の責任 [画像のクリックで拡大表示] |
旧商法においては、取締役の損害賠償責任について、委員会等設置会社とそれ以外の会社との間で、その性質に大きな差異が生じていた。具体的には、委員会設置会社では取締役の損害賠償責任は過失責任とされているのに対し(旧商法特例法21条の7、21条の21)、それ以外の会社では取締役の損害賠償責任の多くが無過失責任とされ、委員会設置会社の取締役の方が責任が軽い、という問題が生じていた(旧商法266条1項1号から4号まで)。
しかし、こうした状況に対しては、さまざまな批判がされていた。「会社の選択した機関の違い(委員会等設置会社なのか、それ以外の会社なのか)によって、取締役の責任の性質に違いを設けるのは合理性がない」、「法律上の原則としては、過失責任(自らに過ち(過失)がなければ責任を負わないという意味における自己責任)が原則であり、無過失責任は重すぎる」といったものだ。そこで、会社法では、会社の機関の差異により取締役の責任の性質を設けることはせず、委員会等設置会社以外についても過失責任を原則とすることとし、制度間の取締役の責任論に関する規定の整合性を図った(会社法423条)。この取締役の責任に関する規定をまとめると図1のようになるが、ポイントは以下の点である。
・競業取引や利益相反取引の過失責任化
商法では、取締役の責任が問われやすい取引(会社に損害が生じやすい取引)を類型化して、取締役会の承認を要求するなど、一定の制限を加えてきた。例えば、取締役が会社の事業と競合するビジネスを行う会社の取締役となる場合や、取締役と会社の利益が相反する取引(会社が取締役に対して金銭貸付をする場合など)について、旧商法では取締役会の承認を必要とし、また、当該取締役が会社に損害を与えた場合には、無過失責任であるとしてきた。
会社法においても旧商法と同様に、利益相反取引については会社に損害を与える可能性が高いことから、取締役会の承認(356条1項、365条 取締役会非設置会社は株主総会による普通決議)を要求している。もっとも、旧商法が採用していた無過失責任については原則としては採用しなかった。具体的には、一定の取締役・執行役は任務を怠ったものと推定される旨の規定を置き、過失責任の原則にあらためた(423条3項)。
・利益供与の禁止
日本では戦後、いわゆる総会屋に対して会社が金銭などを交付し、利益を供与する事件が多発した。そのため旧商法では、株主に対して利益供与を行った取締役や、それに関与した取締役の会社に対する責任について、無過失責任が採用されていた。
これに対して会社法では、利益相反取引と同様に、取締役・執行役は原則として任務を怠ったものと推定される旨の規定を置き、過失責任の原則に改めることとした(120条4項)。従来に比べて総会屋による株主総会支配が下火となったこともあり、法律上の原則に立ち返って過失責任としたのである。
しかし、会社法成立のための国会審議において、総会屋が再度、社会問題化することなどへの懸念が強く表明された。そのため、結局、当該利益の供与をした取締役自身については、無過失責任に戻された(120条4項)。
(2)責任の免除・限定に関する制度の整理
旧商法においては、取締役に責任があると認められる場合において、(1)総株主の同意による責任の全部免除(旧商法266条5項)、(2)競業取引・利益相反取引や株主への利益供与など類型化された行為を除く定款または法令違反による会社に対する責任についての株主総会による責任の一部免除(266条7項)、(3)定款規定+取締役会決議による責任の事後の軽減(266条12項)、(4)定款+責任限定契約による事前の軽減(社外取締役の場合のみ、266条19項)を認めていた(旧商法266条1項5号)。
会社法においても、取締役の会社に対する責任は、総株主の同意がなければ免除できないのが原則である(424条)。もっとも、会社法では競業取引・利益相反取引についても総株主の同意(上記(1))以外の方法による責任の一部の免除(上記(2)など)を可能としつつ(425条~427条)、取締役が自己のために利益相反取引をした場合や株主への利益供与等については行為の問題の大きさから責任の一部免除を認めないこととするなどの修正を施している(428条1項)。
これらをまとめると図2のようになる。ポイントは以下の通りである
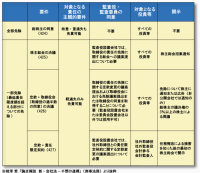
▲図2 取締役の責任免除制度 [画像のクリックで拡大表示] |
・株主総会による免除
取締役に故意または重大な過失がなかった場合は、各監査役または各監査委員の同意を得た上で、株主総会の決議をもって、以下の分までその責任を免除できる(425条1項)
代表取締役・・・年俸の6年分
社内取締役・・・年俸の4年分
社外取締役・・・年俸の2年分
・取締役決議による免責
監査役設置会社または委員会設置会社では、一定の軽微な行為については取締役会による免責を認めた。具体的には、定款に定めがあり、利益相反取引などの行為に当たらず、取締役に故意や重大な過失もない場合で、事案の内容や取締役としての職務の執行状況その他の事情を勘案して特に必要があると認められる場合には、取締役会は取締役の責任を一部免除できる(426条)。なお、免除できる額は上記株主総会の決議による場合と同じである
こうした取締役の責任の免除にかかわる制度は、取締役の責任を厳しくしすぎると会社の取締役のインセンティブに大きな影響を及ぼす反面、責任を軽減しすぎるとコーポレートガバナンスの観点から問題が生じる。制度自体は日常の事業活動に大きく影響しない、一見、地味なものであるが、会社のコーポレートガバナンスや取締役のインセンティブに対する考え方など、会社の基本方針が明確に現れる重要な問題であるといえよう。
以上のように会社法では、制度の不整合を回避するための修正や、取締役の責任免除・限定にかかわる修正が施された。このほか、取締役の責任に関して会社法では、株主代表訴訟制度の乱用を防止するための手当(847条1項但し書き)や、不提訴理由の開示制度の設置などの整備を行っている。
会社法の今後について
以上のように、会社法では従来に比べて取締役の責任に関する規定が整理・明確化されたとはいえ、株主代表訴訟制度が充実したことも考えれば、今後より訴訟提起は増えることが予測される。前述したように、取締役の責任が問題となる事案はその時代を象徴するケースが多く、今後は敵対的買収やTOB(株式公開買い付け)あるいはM&A(合併・吸収)の失敗などにおける責任追求が増えるのではないか。また、企業不祥事を発見できなかった社外取締役の責任や内部統制システムの構築に関する各取締役の責任などは今後も問題になろう。
複雑かつ高度な知識が要求される事案においては、裁判所は経営判断原則により慎重に判断するものと予測される。しかしその一方で、内部統制に関する裁判所の厳しい態度などを考えれば、大きな流れとしては取締役の責任を裁判所は重く考える傾向にあるといえる。取締役の地位にある者は、この点を肝に銘じて日常の職務にあたることが求められているといえよう。
(次回へ)
|





















































