戦略なきアウトソーシングや分社化によって、弱体化した情報システム部門。
だが、システム部門の再起なくして、日本企業の復活はあり得ない。
システムの企画力やベンダーとの交渉力を“再生”せよ。
システム屋の“魂”を若い世代に伝えろ。
自らの存在意義を取り戻すべく、動き始めたシステム部門の奮闘を報告する。
| Part1 実録:システム化の“精神”を若手に----クレディセゾンの選択 Part2 挑戦:企画力と選球眼を磨き、空洞化に立ち向かえ Part3 列伝:新しいシステム部門を創れ----改革に取り組む5人の男たち |
本記事は日経コンピュータ2002年11月4日号からの抜粋です。そのため図や表が一部割愛されていることをあらかじめご了承ください。なお本号のご購入はバックナンバー、または日経コンピュータの定期ご購読をご利用ください。
Part.1 実録
システム化の“精神”を若手に----クレディセゾンの選択
開発・運用を外部ベンダーに任せるのは時代の流れ。だが、それにより肝心のシステム企画力が衰えてしまっては元も子もない。外部委託を続けると、既存システムの設計思想が次第に分からなくなる。ITスキルが低下し、ベンダーとの交渉力も弱まる。クレジットカード大手のクレディセゾンはこうした危険をいち早く察知し、2年前から若手教育に力を入れ始めた。自社システムの“生い立ち”を学ぶ会を開いたり、ノウハウを継承しやすいように人員を配置している。同社を例にシステム部門の空洞化を防ぐ取り組みを見てみよう。
東京・池袋の超高層ビル「サンシャイン60」に本社を構えるクレディセゾン。9月25日の昼休みが終わって20分ほどたつと、情報システム部員の半数が自席を離れ、移動を始めた。その数ざっと20人。ほとんどは入社5年以内の若手だ。
彼・彼女らが向かった先は、システム部門と同じ53階にある会議室。そこで午後1時30分から開かれる定例の「勉強会」に参加するのが目的である。
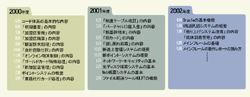 |
| 図1●定例の勉強会で情報化の精神を若手に伝える |
勉強会というと、「Webサービス」や「ディザスタ・リカバリ」といった最新ITを習得する場を想像する向きもあるだろう。だが、クレディセゾンのそれは違う。同社の勉強会で取り上げるのは、基本的に自社のシステムに関することだ。この日のテーマである「メインフレームの動作レポートの読み方」も、この原則にのっとって進められた(図1[拡大表示])。
「このシステムの処理が所定時間内に終わらなかった場合は、次のような原因が考えられます」。メインフレームの運用を委託しているセゾン情報システムズから招いた講師は、動作レポートの読み方を実際のシステムに照らし合わせて説明していく。クレディセゾンのシステム部員たちも真剣なまなざしで資料を追う。1時間半にわたって、密度の濃い時間が流れた――。
「いくらなんでも若すぎる」
クレディセゾンのシステム部門は2年前から,こうした勉強会を月1回ペースで開いている。「システムの過去を知らなくても日常業務は回る。だがシステムを作った際の“精神”を若手に伝えておかないと、次のシステムを企画する力が失われてしまう」。こう考えた栂野恭輔情報システム部長の音頭で勉強会は始まった。参加は各人の自由意思だが、40人ほどいる部員のうち、若手を中心に15~20人は毎回参加している。
この勉強会は、栂野部長の危機感の表れでもある。「システム部員の大半は入社後3年以内の若手。これはいくらなんでも若すぎる」。2000年2月に現職に就き、システム部門を率いることになった栂野部長は真っ先にそう思ったという。栂野部長自身も当時39歳。1996年に課長として経理部門から異動してきた彼には、その時点で4年のシステム経験しかなかった。4人いる課長も全員40歳以下だった。
クレディセゾンは昔からシステム部門とユーザー部門の人材交流が活発だったこともあり、80年代半ばに構築した基幹系システムの設計思想や全体像を理解しているベテラン社員は、ほとんど残っていなかった。
「自社のビジネス・スタイルと情報システムを合致させるという使命をこのままでは果たせなくなる」。栂野部長はあせった。「経営がビジネス・スタイルの変更を望んでも、全面刷新が必要なのか、部分改修ですむのかが判断できない恐れがあった。これはシステム企画を強化する以前の問題だ」。
クレディセゾンのシステム部門が既存システムの成り立ちに疎くなったのもムリはない。同社は80年代初頭からシステムの開発と運用を、同じグループのセゾン情報に委託している。それ以降、システム企画がシステム部門の中核業務になった。既存システムの保守案件の取りまとめもしているが、プログラミングは一切しない。どのような機能を追加するかを決めて、実際の作業はセゾン情報に依頼していた。
勉強会で“過去”を訪ねる
「過去のシステムを知らないと、企画力が落ちてしまう」。こう懸念した栂野部長はさっそく手を打った。それが部長就任から3カ月たった2000年5月に始めた定例の勉強会である。
まずは主要なサブシステムを毎回一つずつ取り上げ、構築当時を知るセゾン情報のエンジニアに説明してもらうことにした。「何のためにこのサブシステムが別のサブシステムと連携しているか」や「なぜこの機能はサブシステムとして切り出す必要があったのか」などを語ってもらった。「システムを構築した時の苦労を今から体験することはできないが、当時の考えを知ることはできる」と栂野部長は期待した。
第1回の勉強会では、クレディセゾンの業務の基盤である、加盟店コードの体系を取り上げた。同社にとって“生命線”ともいえる加盟店管理業務の基礎を学ぶためだ。勉強会では、コード体系がどのような歴史的経緯で現在の形になったかを重点的に解説した。
加盟店コード体系は、クレディセゾンが業務を拡大するごとにどんどん複雑になっていった。「コード体系が複雑化した理由を知らないままでも、加盟店の追加・削除といった日常業務はこなせる。だが将来、基幹系システムを刷新するときに支障が出るのは必至だった」。
勉強会の開催を決めたとき、栂野部長は「参加者はせいぜい数人」と見積もっていた。もともと「システム部員のだれよりも自分が過去のシステムを学ぶ必要がある」と思って始めた、自由参加の勉強会だったからだ。
ところがシステム部員の反応は、思いのほか良かった。第1回から15人以上が参加した。回を重ねるに連れて、システム部員からは「今度はこのテーマでやってください」といった要望が上がるようになった。「日常の業務をこなす過程で、若い部員も過去を知ることの重要性を感じていたようだ」と栂野部長は笑みを浮かべる。
システム部門の空洞化が危険水域に入った。開発や保守・運用の作業をITベンダーやシステム子会社に任せた結果、肝心のシステム企画力やプロジェクトマネジメント力に陰りが見える。少数精鋭を貫いたあまり、組織としての新陳代謝にも支障が出ている。今すぐシステム部門の再生に乗り出さなければ、企業経営にシステムを生かす道が閉ざされてしまう。こうした危機感に駆られ、すでに一部の企業は動き始めた。明治生命、北海道銀行、パソナ、協和発酵などの取り組みを追った。
今年4月、消費者金融準大手の三洋信販は、日本IBMとのアウトソーシング契約を延長した。10年前に日本IBMとの間で結んだアウトソーシング契約の期間満了に伴う措置だ。三洋信販は1992年3月、システム開発から保守・運用に至る全業務を日本IBMに10年間200億円で委託し、国内における包括アウトソーシングの先駆者とされていた。
今回の契約更改は三洋信販にとって、必ずしも満足いくものではなかった。「これまでのメインフレーム絶対主義を見直し、機敏にシステムを構築できる枠組みを作るべきだった」。契約更改の直後にITベンダーから招かれた海津暁夫執行役員戦略本部副本部長はこう断言する。昨年4月に旧マイカル・グループの信販会社マイカルカード(現ポケットカード)を傘下に収めるなど、三洋信販のビジネスは目まぐるしく変化している。だが、「300万ステップにも及ぶ現行の基幹系は徐々に保守性が悪化し、経営の変化に追随しにくくなっていた」。
ところが、10年間にわたるアウトソーシングは、三洋信販のシステム部門から次世代システムを企画する“力”を奪っていた。このため契約更改を前に日本IBMに抜本的な改革を要求できなかった。「IBMもそれまでと同じメインフレーム中心の開発・運用形態しか提案してこなかった」。
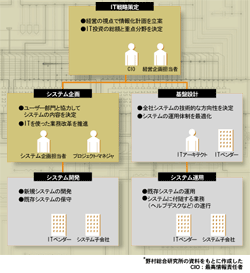 |
| 図3●企業の情報化に必要な五つの機能 |
結局、三洋信販は10年前の契約をほぼ踏襲した格好で再契約せざるを得なかった。その代わり、今回は契約期間を2年に限定した。「その間にシステム部門を立て直し、次はより理想的な契約を結べるようにする。IBM以外のベンダーに参加してもらうことも視野に入れている」と海津執行役員は決意を語る。
「経営の要望をシステムに翻訳する能力と、適正な技術やコストを見極める能力の二つはなんとしても社内に持たねばならない」と海津執行役員は考えている。「業務知識とITスキルを兼ね備えた人材の育成には時間がかかるが、それでも1~2年以内に結果を出したい」。
企画特化で“勘所”を忘れる
今、日本企業の多くは、「本業集中」の旗印を掲げ、間接部門をスリム化している。システム部門もその例外ではない。
システム開発や保守・運用をITベンダーに長期アウトソーシングする企業や、システム部門を別会社化したり、売却する企業は後を絶たない。「本社に残したごく少数のシステム企画担当者がシステム子会社やITベンダーと協力しながら、全社のIT戦略を推進する」というのが、ここ数年の流行のスタイルだ。野村総合研究所(NRI)の淀川高喜ITマネジメントコンサルティング部長は「システム開発や運用は外部に任せることも可能だが、IT戦略の策定とシステム企画だけは企業内に残しておかなくてはならない」と断言する(図3[拡大表示])。
だが、ここに一つの罠がある。「少数精鋭で企画に専念」と宣言し、現場と距離を置くと、システム企画の勘所がわからなくなってしまうのだ。
続きは日経コンピュータ2002年11月4日号をお読み下さい。この号のご購入はバックナンバー、または日経コンピュータの定期ご購読をご利用ください。
![]()
今回のシリーズ特集では、コスト編、開発編、人・組織編の三つのテーマで、システム部門が抱える代表的な悩みの解決策を探りました。できあがった誌面はテーマごとに分かれていますが、実は、取材では三つのテーマを同時に質問しています。そのためシリーズ最後の今回は、数カ月前に取材した内容をまとめた部分もありました。
取材から執筆までの期間が長いと、どうしても印象や記憶が薄れてしまします。記事の内容を決めることの次に、この「記憶との戦い」が大変でした。例えば、Part1でご紹介したクレディセゾンに最初の取材をしたのは7月22日ですが、実際に本文をまとめたのは10月に入ってからです。もちろん、いい加減な記事を書くことはできませんので、メモが不十分なところはすべて取材先へ再度確認しました。自信を持ってお読みいただける記事に仕上げております。(矢口)





















































