中田課長の指示で、桜井君に同行し菅原機械を訪問した内藤主任ですが、菅原機械の専務と桜井君との親密ぶりに驚きます。しかも1時間、世間話ばかりで仕事の話は一切なし。内藤主任の混乱は深まるばかりです。トイレのため席を立った専務は、競合する琵琶通の提案書を机の上に残します。「見てはイカンぞ」と言われても、見ようとする桜井君。それを止めようとした内藤主任ですが…。
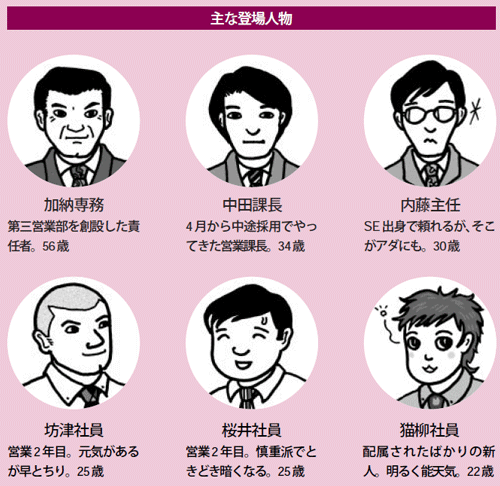 |
専務がハンカチで手を拭きながら部屋に戻ってきたとき、すでに書類は机の上に戻されていました。
「あー、すっきりしたなあ。君たち、まさか、この書類見てないだろうね?」
「もちろんですよ。専務。なにおっしゃってるんですか。では、僕たちはこれで失礼します」
「そうか、じゃ、また遊びに来てくれ。待ってるよ」
桜井君はさっさと帰ろうとします。専務もいすに座ることもなく、部屋の外に出てしまいました。急いでエレベータホールまで専務の後を追う2人でした。
「では、ここでな」
「ありがとうございました」
「来週の提案、期待しているよ」
「必ずご期待にお応えいたします」
「契約しないと、またサクちゃんと飲みにいけんからな。あっはっは」
「いえいえ、失注いたしましても是非お誘いください。僕と専務の仲じゃないですか、そんな水臭いこと言わないでくださいよ」
「わははは、とにかく仕事、取れよ」
「はい、では失礼いたします」
電車に乗った2人は小声で話し始めました。
「結局、琵琶通の見積もり、見ちゃったね。それどころか提案範囲や詳細部分まできっちりノートに写して…良かったのかい。サクちゃん」
「主任は専務のハンカチ、見ましたか?」
「えっ? 何、ハンカチ?」
「部屋に戻ってきたときのハンカチですよ。全く濡れてなかったでしょ」
「あ、いや、見てなかった…」
日頃はぼーっとしているように見える桜井君ですが、その観察力に内藤主任は驚きました。
「トイレには行ってなかったんです。多分」
「え? そうだったのか。でも、どうして…」
「どうして競合の見積もりを見せてくれたのか? それは僕も分かりません。なんか気に入ってくれたんです」
「うーん…」と腕を組み、首をかしげる内藤主任です。
「でも、人間はいきなり仲良くなれるものかい。サクちゃんは何回専務と会ったんだい? 今日で何回目?」
「えーっと、5回目…かな」
「最初は? 何がきっかけ?」
「先月のセミナーですね。申し込みがあったのですが、欠席されたのでレジメを届けに行ったんです」
「それだけで? 本当にそれだけかい?」
「うーん、あとはずっと世間話ですね」
「むむ」と言っただけで黙り込む内藤主任です。
「課長、競合の見積もり価格を入手できました!」
「よくやった、桜井」と中田課長。
「すごいですね。桜井先輩、うちのお客さんも予算、教えてくれないかな」と猫柳君がうらやましがります。
「バカ、それができないから、苦労してんじゃないか。今日は内藤主任が登板したんですか? さすが内藤さんですね」 感心する坊津君でした。
『自分はなにもしていないのに…』苦笑いする内藤主任でしたが、内心は穏やかではありません。それを見てか、中田課長は内藤主任を会議室に呼びました。
 |
| (イラスト:尾形まどか) |
「桜井はお客さんが好きなんだよ」
外の明かりを見ながら中田課長は話し出します。
「だからお客さんも桜井のことが好きになったんだ。基本はそういうことだ」
「お客さんが好き…ってどういうことですか?」
「ま、いい。その話は後回しだ。ところで内藤は最近の自分の失注をどう分析する? 失注が連続してるよな」
「そうですね。いつも、いいセンまで行くんです。決勝まで残るんです。でも取れない」
内藤主任は一気にしゃべりだしました。
「桜井、坊津、猫柳は提案さえさせてもらえないケースが多いじゃないですか。僕のほうが受注に近いのに、どうして取れないんでしょうか? なんだか坊津や猫柳、それに桜井も受注できそうだし。偶然でも悔しい」
中田課長は黙って聞いています。
「僕のどこが悪いんでしょう?」
「それを考えさせるために同行させたんだよ」
「えっ」
「人間として信用してもらうためには、どうすればいいか。考えたことがあるか?」
「いえ、あまり…。正直考えたことがありません」
「それはなぜだ?」
「課長がいつも『顧客とリレーションを持って信頼関係を勝ち得るのが営業の仕事だ』とおっしゃっているので、僕だって意識しています。でも僕には技術論があります。開発に携わっていたわけですから、その辺りを話せば、お客様のガードは下がるんです」
「そうだろう。それはよく分かる」
「で、どこが悪いんですか?」
「全部、悪い」中田課長は内藤主任の目を真っ直ぐ見て言い切りました。「では、技術のない桜井は何をもって客のガードを下げるんだ? 考えてみろ」
内藤主任は少し憤慨しています。
「よく分かりませんが、専務との話からすると、話題が合ったことだけですね。息子さんが同い年とか…」
「そうだ。以前に桜井に聞いたんだが、桜井と専務の家は近所らしい」
「じゃ、偶然じゃないですか。そんなの営業じゃないですよ。それなら僕も、自宅が近くて息子さんが同い年の役員がいる会社に営業に行けってことですか?」
「桜井の家の犬と専務の犬の散歩コースも近いらしい」
「ますます偶然だ。そうじゃなきゃ優秀な営業マンはみんな犬を飼ってるって話ですか」
「そうじゃない。冷静になれ。いつもの君らしくないな」
上着を脱いでから中田課長は話し出しました。
「桜井は裸になっている。お前はなってない。そういうことだ」
「昨夜、飲みにいって裸踊りでも…」
「バカ、そうじゃない」
思わず中田課長は吹き出しました。
「いいか、それだけの話題を一致させるために、桜井はどれだけ自分の話をしたと思う?普通、取引実績もない営業マンに自宅の住所まで言うわけがないだろう。たくさん自分の話をして相手の話を引き出した結果が、今日につながったんだ。俺もまさか、桜井が競合情報まで入手できるとまでは思わなかったが」
中田課長はさらに続けます。
「技術論を展開したところで、営業が越えるべき最初のハードルをお前は飛べていないんだ。迂回している。お前の資料は競合会社に漏れている可能性が高い」
「げっ」
「今日の桜井の例を見てみろ。逆のケースがあると思わないか?」
「確かに…そ、それは…」
「我々の商談には3つのハードルがある。1つ目は人間のハードル、次が技術のハードル、最後がビジネスのハードルだ。それらを飛び越えるたびに、お客さんはより本音で話をしてくれる。今回は桜井が成功したが、うちの営業は皆、1つ目のハードルでつまずいている。これこそ営業が越えなければならないハードルだ。内藤はそれを迂回して技術のハードルを先に越えてしまっている。だから、お客さんはそこそこ話をしてくれるが、最初のハードルを見逃しているため、それを越えた競合会社に負けるんだよ」
「だから一次審査を突破しても、決勝では負けるんですね…。僕はもうダメじゃないですか」
徒労感が内藤主任に襲い掛かりました。『何やってたんだろう。今までの自信に何の意味があったんだろう』
「そんなことはない。そこにさえ注意すれば、内藤は鬼に金棒なんだよ。1つ目と2つ目のハードルを一気に飛び越える営業になれる可能性を秘めているんだ」
内藤主任は顔を上げました。「大丈夫ですかね。僕はそんな営業マンになれますか?」
「大丈夫だ。安心しろ。そこに気付けばトップ営業は近いぞ」内藤主任の背中をたたき、笑顔で会議室を出る中田課長でした。
「で、なんでサクちゃんはそんな仲よくなったんだよー。教えろよー」「そうですよ。秘訣を教えてください」
第三営業部のオフィスは、若手の3人でわいわい盛り上がっていました。
「なに騒いでいるんだ」と部屋に戻ってきた中田課長。
「桜井がですねー、競合の見積もりを教えてもらったのは自分が気に入られたからだって言うんですよ」坊津君が桜井君のおなかにパンチを入れながら言いました。
「ほんとだよー。飲みに行って仲良くなったんだよ。酔っ払っちゃってさ、裸踊りしたらしいんだよな」
それを聞いた中田課長は渋い顔です。「お前たち。その話、内藤主任に言うんじゃないぞ」(次回に続く)
|
|





















































