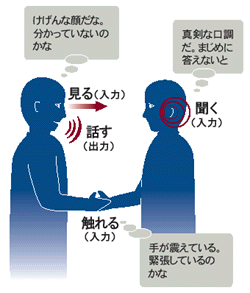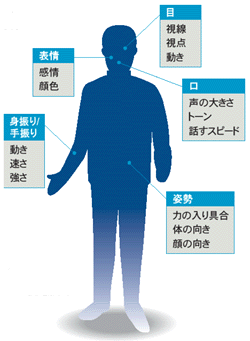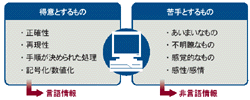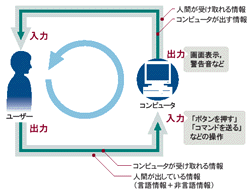![]()
用途や使い方が合っていれば,今のコンピュータはとても便利だ。特に,GUIが果たしている役割は大きい。作業机やごみ箱,フォルダなど,身の回りにあるものを模して作られたGUIのおかげで以前よりも多くのユーザーがパソコンを使えるようになった。コンピュータは身近なものになり,多くの人がコンピュータを日常的に使うことに慣れた。
ただし,現在のコンピュータの使い方は,ユーザーの頭の中にある「こうしたい」をユーザー自身が整理して,コンピュータに分かる形に翻訳して操作している。だから,コンピュータを使えないでいる人もけっして少なくはない。コンピュータが人間の活動を支援する道具という考えに立てば,ユーザーが担っている「コンピュータに分かる操作に置き換える」役割を,部分的にでもコンピュータに受け持ってもらいたいところだ。そうすれば「今よりももっとさり気ないユーザー・インタフェースが可能になる」(慶應義塾大学 環境情報学部 教授の安村通晃氏)。
必ずユーザーが操作を考える
人間がコンピュータを使う場面を考えてみよう。それぞれが受け持つ役割を整理すると,最初の働きかけが一方向であることに改めて気付かされる(図1[拡大表示])。頭の中にある「こうしたい」をコンピュータに実現してもらうには,常に人間からコンピュータに命令を送るという手順が必要だ。
マウスでアイコンをクリックしてファイルを選択したり,関連付けされたデータファイルのアイコンをダブルクリックして,アプリケーション・ソフトで開くといった操作は,すべてユーザーからコンピュータへの指示である。これを受けて,コンピュータはしかるべく処理する。そして,処理結果を何らかの形で出力し,ユーザーに示す。
もし,コンピュータがもっと積極的にユーザーの求めるものを理解するようになれば,人とコンピュータの関係性は大きく変わるだろう。コンピュータがユーザーを観察し,ユーザーの気持ちや考えを理解できれば,ユーザーが漠然と持っている「こうしたい」という意図をうまく読み取り,適切に処理してフィードバックを返してくれるようになるかもしれない。その行き着く先は,「操作」という概念のないコンピュータだ。もしそれが実現できれば,本当の意味で誰でもコンピュータを使えるようになる。
あいまいな非言語情報は苦手
しかし,今のコンピュータには人間の感情や様子を理解する能力がない。例えば,人間同士が会話するときに相手をどのように観察し,理解しようとしているかと比べてみると,コンピュータに同じことを担わせるのがどれほど困難かが分かる(図2)。
交わされる言葉は文字に変換できる情報だ。もしかすると,会話によってはそのままでも今の音声認識技術で聞き取れるかもしれない。しかし,話し言葉は実際には文法的に間違っていることもあるし,省略されている部分が多かったり,語尾があいまいになって聞き取りにくいこともある。人間なら文脈から類推できるが,コンピュータがうまく認識できるケースはまれだろう。それがカジュアルな場の話し言葉であればなおさら難しい。「日常のコミュニケーションには,それほどフォーマルな場面は多くない」(NTTマイクロシステムインテグレーション研究所 ユビキタスインタフェース研究部 ホームコミュニケーション研究グループ 主幹研究員の野島久雄氏)。つまり,ユーザーの日常から相手を理解するための情報を得ることは,ほとんどできていないのだ。
しかも,人間は受け取っているのは相手が口にした言葉だけではない。例えば口調だ。口にした言葉は同じでも,声のトーンや大きさ,話すスピードなど,話し手の真意を考える上での材料はいろいろある。
表情やしぐさにも,相手の真意が表れていることが多い。自分が話している相手が「けげんそうな顔をしている」ことが見て取れれば,「もう少し分かりやすい言い方に変えて,もう一度繰り返す必要がある」と判断できる。
もちろん聞き手も言葉だけでなく,他の情報も集めている。「口ぶりに熱がこもって真剣味を増してきた」と分かれば,「うかつな受け答えはできない」と考える。身振りや手振り,体や顔の向き,足の組み方や手の置き方といった姿勢,座っていても表れる微妙な体の動きなども,言葉だけではうかがい知れない相手に関する情報になる(図3[拡大表示])。意図的に表情や口調を作って,相手に本心を読まれないようにすることもできる一方で,ふとしたはずみで顔に心理状態が表れて,相手に伝わってしまうこともある。
時には,言葉以外の情報が言葉以上に重みを持つこともある。その端的な例が1960年の米大統領選の行方を決めた,Richard M. Nixon対John F. Kennedyのテレビ討論である。
このテレビ討論までは共和党の候補であるNixonが現職の副大統領として重ねた外交政策の成果を武器に,有利に選挙戦を進めていた。しかし,積極的に遊説を重ねていたNixonはテレビ討論に疲れ切ったまま出席してしまった。大汗をかきながら,疲れた様子で討論するNixonに対し,メークやスーツの選択にもそつがなく,健康的で堂々とした態度で討論をこなしたKennedyは,テレビ討論の視聴者に「大統領にふさわしい」と印象づけることに成功した。
討論終了後,Nixonは勝利を確信していたという。実際,ラジオの聴取者はNixon有利と判断したという調査もある。しかし,討論で交わされた言葉のやり取りよりも,テレビから伝わった見た目の様子が大統領選の行方に大きく影響した。
コンピュータは,こうした言葉にならない情報を扱えない(図4[拡大表示])。言葉で表すことができる情報は言語情報であるのに対し,そうした言葉にならないものの,何らかの形で表現される情報が非言語情報である。コンピュータが扱えるのは言語情報のみ。それも,言語情報のごく一部でしかない(図5[拡大表示])。こうしたギャップが「出力がほぼ視覚情報のみに限られているなど,人間にとっては他の感覚を使えない不自然さが実は大きな負荷になっている」(大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 システム科学領域 教授の佐藤宏介氏)と見る向きもある。ただ,あいまいさを許さないことで,コンピュータは客観的で正確な処理を実現できているというのも事実だ。