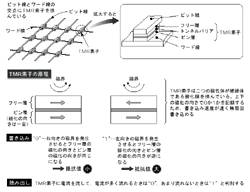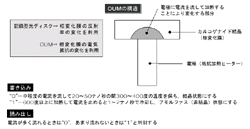無制限に書き換え可能なMRAM
FeRAMのように量産が始まってはいないが,磁気記録を応用したユニークな不揮発性メモリーもある。それがMRAMだ。MRAMは,磁性体であるTMR(Tunnel Magneto Resistance)素子を使う(図7[拡大表示])。データの記録は磁化の向きで抵抗値が変わることを利用する。低消費電力で高速に書き込み・読み出しができる。書き換え回数は無制限だ。ちなみに,TMR素子は次世代のハードディスクのヘッドとしても期待されている。
MRAMの問題は,TMR素子の加工が難しいこと。磁性体は半導体とは異なり,加工に化学的な反応を用いることができず,物理的に加工しなければならないため,形状を制御しにくいからである。TMR素子は二つの磁性体層が絶縁体であるアルミニウム酸化膜を挟む構造をしている。電流はこの三層になっている素子を突き抜けるように流れる。そのため素子の形や層の厚みにばらつきがあると誤動作が起こる。また,製造過程で層の間でショートが起こってしまうこともある。
MRAMの書き込み時には,TMR素子の抵抗値を変えるために,絶縁体を挟んでいる磁性体層の磁化方向を変化させる。下層(ピン層)は磁化方向が一定である。磁化方向を変化させるのは上層のフリー層だ。0の書き込み時は,下層と同じ向きの磁界を発生させる。上層の磁化方向は下層と平行になり抵抗値が小さくなる。1の書き込みはその逆で,下層とは逆向きの磁界を発生させ上層と下層の磁化方向を反平行にする。この場合,抵抗値は大きくなる。
読み出し時は,TMR素子に電流を流す。0であれば抵抗値が小さいので多く電流が流れ,1であれば抵抗値が大きいので流れる電流が少ない。この違いで0と1を判別する。
MRAMの動作が高速なのは,磁性体の磁化方向の反転が高速だからだ。また,磁化方向を変える回数に制限がないため,書き込み回数は無限回になる。
トランジスタを不要にできる
MRAMのセル構造は,トランジスタをTMR素子につなぐ選択トランジスタ型が主流だ(図8[拡大表示])。一つひとつのセルをトランジスタで制御できるため消費電力が小さく動作も速い。また,周辺回路を簡単にできる。ただしこの構造は,セルを小さくしにくく大容量化が難しいのが欠点である。
ほとんどのメモリーはスイッチングにトランジスタを使うが,MRAMではトランジスタを使わないで駆動できる構造も開発されている。これをクロスポイント型と呼ぶ。電極を上下に直交するように並べ,交点にTMR素子を配置するため単純な構造にできる。
クロスポイント型は素子を小さくでき,多層に積むことも可能なので,大容量化しやすい。ただし,選択したセルだけを読み出すために電流を流しても,周囲にも回り込み電流が発生してしまうため,周辺回路が複雑になり読み出しに時間がかかるといった欠点がある。
MRAMはこれら二つの構造があるたので,「用途としては大容量化に向く製品と高速な製品というように使い分けていく」(NECシリコンシステム研究所兼基礎研究所の田原修一研究部長)可能性が高いと言う。
今後は,書き込み時の電流を低減することが課題だ。同メモリーの開発を進めている東芝は「現在高いといわれている書き込み電流を3分の1ほどの3mAに低減できた。将来的には1mAにしたい」(同社SoC研究開発センター不揮発性メモリデバイス技術開発部参事の與田博明氏)と考えている。ただし,電流を小さくすると0と1の抵抗値の変化率であるMR比が小さくなってしまい,読み取りにくくなってしまう。消費電流を小さくするには,このMR比を上げるための工夫が必要になる。今のところ,TMR素子を二重にすること(二重トンネル接合)が考えられている。
他の課題としては,微細化のメドが立っていないこと,スイッチングのために発生させる磁界や読み出し信号のばらつきが大きいこと,などがある。
熱を加えてデータを記録するOUM
OUMは書き込み時に熱を加えて記録する不揮発性メモリーだ。米Ovonyx社が開発した。熱によって結晶状態を変化させる相変化材料を使う。記録型光ディスクで使われているものだ。記録型光ディスクは相変化膜の反射率の変化を利用するのに対し,OUMは電気抵抗の変化を利用するのが異なる。
OUMは書き換え回数が1012回程度,セルを小さくしやすい,抵抗変化率が大きいといった点が利点だ。欠点は,書き込み時間が遅いことである。
相変化材料は,熱の加え方によって,結晶状態とアモルファス(非結晶)状態という二つの状態を作る。これらは電流を流したときの抵抗値が異なるため,0と1を記録できる。二つの状態は熱を加えない限り変化しないため,不揮発性を実現できる。
OUMを研究する米Intel社は相変化膜にカルコゲナイド結晶を使う(図9[拡大表示])。カルコゲナイド結晶に抵抗加熱ヒーターを接触させ,電流を流して接触している部分の結晶状態を変化させる。0を書き込むには結晶状態を作る。結晶状態にするには,300~400度の温度を20~50ナノ秒保つ。1を書き込む時は,アモルファス状態にする。この場合は,600度以上の高温に加熱して電流を止めた後,1~2ナノ秒という短い時間で冷却する。
読み出しは,結晶状態の違いにより,電流が流れるときの抵抗値が変化することを利用する。相変化膜に電流を流すと,結晶状態は抵抗値が小さいので電流が多く流れ,アモルファス状態は抵抗値が大きいので電流は少ししか流れない。Intelが採用している0.18μmのプロセスルールでは,抵抗値は,結晶状態で10kΩ未満,アモルファス状態で100kΩ以上ほどだという。