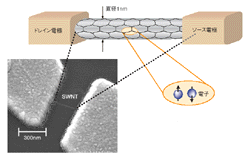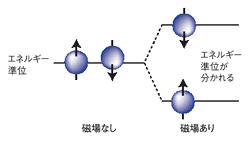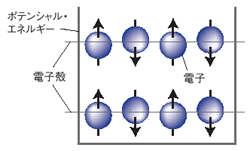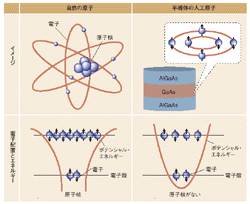![]()
人工原子は,1個の電子で動作する単一電子トランジスタなどナノデバイスへの応用で知られる。しかし最近では,量子コンピュータの計算単位である量子ビットとしても注目されている。電子には2種類の値(上向きと下向き)をとる「スピン」という性質があるが,このスピンを使うと比較的安定性の高い量子ビットを作ることができると考えられるからである。
量子ビットは現在のコンピュータのビットと異なり,同時に0でも1でもある「量子重ね合わせ」の状態で計算が進行する。しかし一般に量子重ね合わせ状態を作ることは難しく,電子のスピン以外では実験に成功する例もいくつかあったが,電子のスピンではこれまで実現されたことがなかった。そのため半導体で作った人工原子を使って,電子のスピンの量子重ね合わせ状態を作る(すなわち量子ビットを作る)競争が世界中で行われてきた。
今回のカーボン・ナノチューブによる人工原子の実現は,電子スピンによる量子ビット実現のチャンスを広げるものである。またカーボン・ナノチューブが細長い形状をしていることから,分割して複数の量子ビットを実現する上で有利ということも想定される。
ただし,理化学研究所と科学技術振興機構もまだ電子スピンの量子重ね合わせ状態を実現してはおらず,半導体の人工原子と比べてどちらが有利かは予断を許さない。
原子内の電子と同様の振る舞いを確認
今回の人工原子は,直径1nm,長さ300nmのカーボン・ナノチューブで実現した(図1[拡大表示])。チューブの両端に電極があり,その間に電圧を加えることによって,チューブ内に電子を1個ずつ注入していくことができる。
自然の原子には「エネルギー準位」と呼ぶ定常的な状態があり,ある準位から別の準位に移るときにエネルギー(光)を吸収したり放出したりする。このような量子力学的な振る舞いの典型的な現象が「ゼーマン効果」である。これは原子に磁場をかけるとエネルギー準位が分裂する現象で,電子が1個の場合はスピンの向きが二つあることに対応して準位も二つに分かれる(図2)。
電子が複数ある場合には,電子間の相互作用が絡んでエネルギー準位のより複雑な分裂現象が見られる。今回はそのいずれの場合も確認した。研究の中心となっている理化学研究所の石橋幸治主任研究員は,これまでの半導体による人工原子の実験に比べ,ゼーマン効果をより明瞭に確認できたとしている。
また,自然の原子は「電子殻」を持つ。これは,原子核の周りに存在する電子の配置を示すもので,最も内側の殻に2個,その次の殻に8個,といった構造を採る。例えば電子1個の原子はH,2個はHe,そして10個がNeである。これにより,殻がちょうどいっぱいになる電子2個や10個の原子(希ガス族)は,安定していてイオン化しにくいという化学的性質を持つ理由が説明できる。カーボン・ナノチューブを使った人工原子でも,電子殻が存在することを確認した。ただし自然の原子と違い,電子は一つの殻に4個ずつ入る*。これは,人工原子内のポテンシャル・エネルギーが自然の原子や半導体人工原子と違って,図3のような形をしていることによる。
これまで固体素子による量子ビットでは,ジョセフソン接合を利用したものや隣り合う二つの人工原子のいずれに電子がいるかを0と1に対応させたものが実現されている。しかし,いずれも量子重ね合わせ状態を維持できる時間は数ns~数十nsと短く,その改善が課題になってきた。それだけに電子のスピンを使った量子ビット実現への期待は大きい。
人工原子とは何か自然の原子と人工原子の最大の違いは,人工原子には原子核がないことである。人工的に原子を作る初期の試みには,原子核相当のものを半導体の中に作り,その周囲に電子が束縛されるというアイデアもあったが,実現されなかった。現在では半導体の構造を工夫することによって,原子核と同様の束縛力を作り出している*A。
図A[拡大表示]では,自然の原子と半導体による人工原子を比較した。自然の原子では,原子核(正の電気)が作る引力によって電子(負の電気)が周囲に引き止められている。これに対して半導体人工原子では,AlGaAsの円盤2枚でGaAsの円盤(これが人工原子になる)をサンドイッチにする。すると中央にはさまれた円盤の上下の界面にはポテンシャル・エネルギーの障壁が生じる。 また,図Aには示していないが,中央の円盤の円周を電極で取り巻いて電圧をかけることにより,円盤の中に回転対称形のポテンシャル・エネルギーが働く状態になる。この結果,電子は中央の円盤内に束縛される。 微小な領域に閉じ込められた電子は,自然の原子の中にある電子と同様の振る舞いを見せるようになる。ただし,人工原子には原子核がないため,ポテンシャル・エネルギーの分布は図A下のように自然の原子とは異なっている。このため,原子内のエネルギー準位ごとに配置される電子は,自然の原子の場合とは数が違ってくる。 |