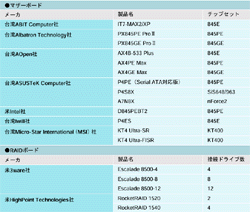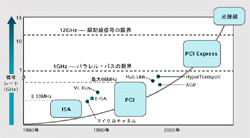待たれる対応ハード・ディスク
2002年11月上旬の時点で,Serial ATAに対応したマザーボードやRAIDボードはかなり揃ってきた(表1[拡大表示])。だが,肝心のハード・ディスクはまだない。これでは宝の持ち腐れである。従来のハード・ディスクのインタフェースをSerial ATA化するアダプタもあるが,単に接続できるようにするだけで,Serial ATAの性能を生かし切れない。
対応ハード・ディスクは,2002年内に米Seagate Technology社の「Barracuda ATA V(ファイブ)」と米Maxtor社の「DiamondMax Plus 9」のSerial ATA対応版が出荷される見込みだ(表2[拡大表示] )。いずれも7200回転/分の製品である。Maxtorは2003年初めにサーバ向けの「MaXLine II/MaXLine Plus II」も出荷する。対応製品をいち早く出荷するこれら2社と対照的なのが,米Western Digital社と韓国Samsung Electronics社である。Intelのチップセットが対応する2003年半ばに合わせて対応製品を出荷する計画だ。
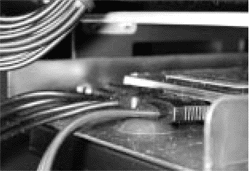 |
| 写真2●富士通のSerial ATA対応2.5インチ・ハード・ディスクの評価機「MHR2020AT」。 2002年10月の「インテル デベロッパ・フォーラム2002 Fall Japan」で披露された |
主にノート・パソコンで使われる2.5インチ・ハード・ディスクの開発も進んでいる。2002年10月に開催された「インテル デベロッパ・フォーラム2002 Fall Japan」では,富士通が試作した2.5インチのSerial ATA対応ハード・ディスク「MHR2020AT」(容量20Gバイト)がデモンストレーションされていた(写真2)。同社は2002年11月に「MHS2030AT」(容量30Gバイト)を一部の顧客に出荷する。これらの評価機は4200回転/分だが,2003年に量産出荷予定の製品は5400回転/分になる見込みだという。2.5インチのSerial ATA対応ハード・ディスクは日立製作所も開発を進めている。2003年末から2004年にかけて製品化する計画だ。
サーバ向けのSerial ATA II
Serial ATAには「Serial ATA II」という派生規格もある。Serial ATAにサーバやネットワーク・ストレージに必要な仕様を追加した規格で,Serial ATAを置き換えるものではない。Serial ATAがパソコン全般に使える汎用の規格であるのに対し,サーバに特化した規格という位置付けだ。
Serial ATA IIは,Serial ATA Working Groupが2002年2月に仕様の策定を開始した。規格化は2段階で行う。まず,転送速度150Mバイト/秒のSerial ATAにサーバに必要な仕様を追加した「フェーズ1規格」を策定し,次に転送速度を300Mバイト/秒に高めた「フェーズ2規格」を策定する。
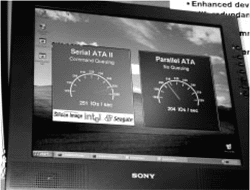 |
| 写真3●2002年9月の「Intel Developer Forum Fall 2002」で披露されたSerial ATAzKのデモ。 コマンド・キューイングに対応していない現行のパラレルATAと比較して,1秒当たりの入出力の回数を約25%増やせたという |
フェーズ1規格は2002年10月に公開された。特徴は「コマンド・キューイング」という機能に対応している点。ホスト・コントローラからデバイスに発行される複数のコマンドをキュー(待ち行列)に格納することで,順不同(out-of-order)実行などによりデータ転送の効率を上げる機能である。すでに,SCSIがこの機能を備えている。フェーズ1規格に対応したハード・ディスクなどの機器は2003年に登場する見込みである。
2002年9月に米国サンノゼで開催された「Intel Developer Forum Fall 2002」では,実機によるSerial ATA IIのデモンストレーションが行われた(写真3)。ホスト・コントローラとして米Silicon Image社の製品を利用し,Seagateが試作したSerial ATA II対応ハード・ディスクとIntelが開発したソフトウェアを用いた。コマンド・キューイングに対応していない現行のパラレルATAと比較して,1秒当たりの入出力の回数を約25%増やせたという。
Intelは2002年10月23日,初めてSerial ATA IIに対応したディスク・コントローラ「Serial ATA Controller 31244」を発表した。ポート数は4個。1万個注文時の単価は22ドルで,2003年1~3月に出荷を開始する。
フェーズ2規格は2003年後半に公開される予定だ。Serial ATAで300Mバイト/秒を実現する規格は2004年半ばに完成予定なので,高速化ではSerial ATA IIが先行することになる。サーバ用途の方が高速化の需要が大きいためだ。フェーズ2規格に対応した機器は2004年後半に登場する見込みである。
|
銅配線を限界まで使うPCI Express |
PCI Expressの目的も,Serial ATAと同じくパラレル・インタフェースの限界を超えることにある。Intelによれば,複数のデータ信号線を同期させるパラレル・インタフェースの信号レートは1GHzが限界だという(図4[拡大表示])。これに対し,シリアル・インタフェースなら銅配線の限界である12GHzまで耐えられる。もし将来,これ以上の信号レートを実現する必要が出てくれば,銅配線はあきらめて光接続を導入する必要がある。
PCI Expressは,Serial ATAと同じ差動伝送方式を採用し,1ビットの双方向の転送に4本の信号線を用いる。この4本の信号線の単位を「レーン」と呼ぶ。1レーン当たりの転送速度は片方向で250Mバイト/秒。PCI Expressではさらに複数のレーンを束ねて高速化できる。仕様では最大32レーンを束ねて使う「x32」まで定められている。
パソコンでPCIスロットの代わりに拡張ボードの接続用に使われるのは,1レーンの「x1」に対応したスロットだ(図5[拡大表示])。4レーンの「x4」と8レーンの「x8」はサーバ向けだという。帯域幅が必要なグラフィックス・ボードの接続用には「x16」のスロットを用いる。チップセットのチップ間接続にもx16インタフェースが使われる見込みだ。
 |
| 写真4●NECが行ったPCI Expressの実機による初めてのデモ。 2002年9月の「Intel Developer Forum Fall 2002」で披露した |
PCI Expressの実機によるデモンストレーションは,2002年9月の「Intel Developer Forum Fall 2002」でNECと米Xilinx社が初めて披露した(写真4[拡大表示])。NECは,PCI Expressの機能を組み込んだASIC(カスタム・チップ)の出荷を2003年初めに開始する。Xilinxはチップは製造せず,PCI Expressの回路設計(IPコア)をチップ・メーカにライセンスする。
設計の難しさを克服できるか
ただ,PCI Expressには懸念材料がある。対応チップやマザーボードの設計の難しさだ。PCIでは扱う信号の動作周波数が33MHzだったのに対し,PCI Expressでは2.5GHzに跳ね上がる。
過去には,主記憶で同じような例があった。Direct Rambus DRAM(DRDRAM)が対応チップセットやマザーボードの開発に手間取る間に,PC133 SDRAMやDDR(Double Data Rate)SDRAMといったライバルに主流の座を奪われたのだ。DRDRAMはシリアル・インタフェースではないが,少ないデータ信号線を高い周波数で動作させるというシリアル・インタフェースに近い特徴を持つ。PC800のDRDRAMで動作周波数は400MHz(データ転送は800MHz)と,従来のPC100 SDRAMの100MHzから大幅に上がった。このためIntelは対応チップセットの開発に手間取り,何度も出荷延期を繰り返した。また,安定動作のため1チャネル当たり当初3本の予定だったメモリ・スロットを2本に削り,拡張性を犠牲にしてようやく実用化されたという経緯がある。
PCI Expressも,マザーボードの設計は条件が非常にシビアになる点が指摘されている。開発に時間がかかれば,普及が後ろにずれ込む可能性もある。