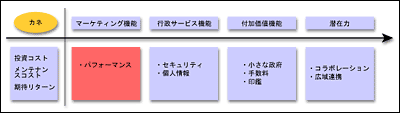| ●今回はマーケティング機能の後半部分を取り上げる。前回までに、マーケティング機能では「ワンストップサービス化」「ブランド化、ショートリスト化」が重要だという考えを示した。そのためには、かけ声だけでなく、具体的な組織を興し、顧客側に立脚して手続きを簡素化するための努力が求められる。また、模倣されるリスクを負う代わりに、鍛えられる中での付加価値の向上についても言及した。 ●さて後半部分では、カネと技術について話を進めよう。一見、投資金額が大きくなれば、技術力もついてくるように思えるが、ブロードバンド時代、バーチャルだからこその一発逆転が期待できる。 |
|
■マーケティング機能と「カネ」の関係 電子自治体にとっての「カネ」とは、「コスト」以外の何物でもない。これが従来の考え方であった。例えば、コミュニティの皆さんから徴収した税金を効果的に使う。ムダを排除するにはどうするか。大き過ぎず、小さ過ぎず。こうした手法が“金太郎飴”的な、良くも悪くも差別化できない自治体を作り上げてきた。 が、よく考えると、効率性(パフォーマンス)はコストとリターンにより決まるものであり、コスト当たりの期待リターンが大きい程、効率的なはずだ。コストを小さくしてもよいし、リターンを大きくしてもよい。大事なのは適切なコストを負担するなかで、相応のリターンを得ることである。目先の利益に惑わされ、大きなリスクを背負い込むことは回避すべきだ。
|
|
Q3 |
マーケティング機能の強化に際して、「カネ」については何に留意しなければならないのか? |
|
A3 |
電子自治体構築後の継続性(メインテナンス)を考え、実績(パフォーマンス)を評価すること |
|
||||||||
 筆者紹介 林志行(りん・しこう)
筆者紹介 林志行(りん・しこう)日本総合研究所研究事業本部・主任研究員。日興證券投資工学研究所を経て1990年より現職。企業のウェブ事情、インターネットを利用したマーケティング戦略に詳しい経営戦略コンサルタント。近著に『中国・アジアビジネス WTO後の企業戦略』(毎日新聞社)、『インターネット企業戦略』(東洋経済新報社)など。個人ホームページ「Lin's Bar」に過去の連載などを掲載。 |