システム部門に対する利用部門の風当たりが強まっている。提供するシステム・サービスの品質が、負担しているコストからみて適正なものなのか判然としないからだ。
もう甘えは許されない。システム部門やシステム子会社は“身内”に対して、サービス品質とコストの関係をきちんと説明する義務がある。
説明の手段として、社内にSLA(サービス・レベル・アグリーメント)を導入する動きがでてきた。日本テレコム、シェル・グループなどの取り組みを追った。
|
ここ数年、コマツの阿部清人インフォメーションテクノロジー部長は、ある問題で悩んでいた。システム・コストの配分を決める根拠が悩みの種だった。
同社の情報システム部門であるインフォメーションテクノロジー部は、全社システムやネットワークの構築・運用といったシステム・サービスの提供にかかった費用を「用役提供費」という科目で各利用部門に付け替えている。“請求書”を受け取った利用部門が、その算定根拠を知りたがるのは、ある意味当然だ。部門ごとの収益が厳しく問われるようになったこともあり、「我々が負担している用役提供費の算定根拠を教えてほしい」との質問を受ける機会がこのところ目立って増えた。
こうした質問にインフォメーションテクノロジー部はきちんと回答できなかった。全社向けシステムやネットワークの構築・運用にかかる費用の総額は当然把握していたが、各部門の負担額をはじき出す根拠があいまいだったからだ。同部は「どの利用部門がどのシステム・サービスをどれだけ使ったか」を示すデータを持っていなかった。疑問を感じながらも、その部門の社員数や売り上げといった指標を基に費用を割り振るしかなかった。
いつまでもこんな状態は続けられない。そこで、コマツのインフォメーションテクノロジー部は「サービス・レベル・アグリーメント(SLA)」に目を付けた。
SLAとはシステム・サービスの提供者と利用者の間で、その内容や品質を取り決める行為を指す。システムの稼働率や障害復旧時間、ヘルプデスクの平均回答時間や即答率といったサービス品質を定量的に評価する指標を導入するとともに、目標値を定める。
「利用部門との間でSLAを結べば、サービスの内容・品質とコストの相関関係を明らかにできる」。コマツの阿部部長はこう考え、昨年から“社内SLA”の導入に向けて動き始めた。
不透明なコストと品質の関係
企業をとりまく環境はかつてないほど厳しい。売り上げが伸び悩むなか、利益を確保するため、各社とも間接費の削減に全力で取り組んでいる。
全社のコスト削減目標は部門ごとの数字に落とされ各部門に割り当てられる。部門ごとの収益管理を徹底しているところほど、利用部門は間接費の削減にやっきになる。「間接費の一つであるシステム関連コストも、削減の対象外ではない」(ベリングポイントの川野克典マネージング ディレクター)。
だがシステム関連コストを削減しようとした利用部門は、すぐに暗礁に乗り上げる。システム部門やシステム子会社に支払っているコストの内訳が判然としないからだ。自部門だけしか使わないシステムなら、利用中止を申し出ることも可能だ。しかしメールをはじめとする全社システムやネットワークなどのインフラに関するコストは、システム部門の“言い値”を払い続けるしか手がない。「システム部門が提供するサービスの品質は負担しているコストからみて適正なものなのか」。多くの利用部門がこうした疑問を抱いている(図1[拡大表示])。
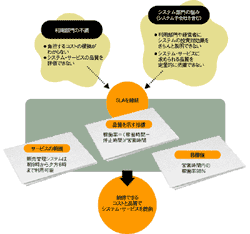 |
| 図1●社内SLAに注目が集まる背景 |
ただでさえ、情報システム・サービスは「費用対効果が判然としない」との批判を受けやすい。『日経情報ストラテジー』が2002年11月、国内の主要企業546社のCIO(最高情報責任者)を対象に実施したアンケート調査でも、現在の課題として「情報化投資の効果の予測・測定」を挙げる回答が61.3%で最も多かった(詳細は同誌2003年3月号の53ページを参照)。
システム部門やシステム子会社にとって、システム・サービスの品質とコストの関係を明らかにすることは、最優先課題と言える。もう甘えは許されない。“身内”への説明責任を果たせないようでは、利用部門や経営の信頼は得られない。
個別のシステム・サービスに対する利用部門の要求水準が判然としない状況では、限られた予算を有効活用することも難しい。どうしても総花的、かつ場当たり的な対応になる。これでは利用部門の満足度が上がるはずもない。
社内やグループ内で締結相次ぐ
そこでSLAの出番が来る。SLAを導入する過程では、システム・サービスの内容と品質が自然と明確になる。品質を定量化すれば、費用対効果の議論がしやすくなる。「高い品質を求めるなら、これだけのコストを負担してもらわなければならない」と要求することも可能になる。
「SLAはアウトソーシング・サービスの利用時にITベンダーとの間だけで結ぶもの」と誤解している読者が多いかもしれない(「SLAを巡る七つの誤解」を参照[拡大表示])。しかしシステム部門と利用部門の間でSLAを結んでもいっこうに差し支えはない。もちろん、社内で正式な契約書を取り交わす必要はない。要は信頼関係の問題だ。
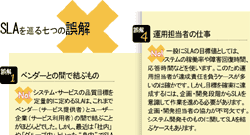 |
| ●SLAを巡る七つの誤解 |
このところ社内でSLAを結ぶ企業は着実に増えている。冒頭で紹介したコマツはほんの一例に過ぎない。
GE横河メディカルシステムの房枝祐志アジア情報技術サービス部長は「SLAで決めた内容をたたき台にして利用部門と折衝すれば、限られた予算の範囲内でサービス品質を最適化できる」と社内SLAの効果を説明する。同社は1992年から社内SLAを導入している。
システム子会社との間でSLAを締結するケースはもっと多い。アサヒビール、キリンビール、シェル・グループ、住友化学、帝人、東京海上火災保険、丸紅などがグループ内でのSLA締結に向けて動き出している。
「支払うコストに見合った品質のサービスをシステム子会社が提供しているかどうかを定量的に確かめたい」(アサヒビールの小熊利章IT部チーフプロデューサー)。各社の担当者はグループ内SLAの導入意図をこう説明する。品質を定量的に評価する指標がなければ、コストを最適化できるはずがない。
以下では、社内/グループ内SLAを駆使して、システム・サービスのコストと品質を最適化する方法を紹介する。
まず次ページからの「Part1:事例編」で日本テレコムとシェル・グループの取り組みを紹介する。日本テレコムは社内のシステム部門と利用部門の間でSLAを結んだ事例。もう一つのシェル・グループは、システム会社とグループの事業会社の間でSLAを結んでいる。
52ページからの「Part2:実践編」では、せっかく取り交わしたSLAを形骸化させないためのポイントをまとめた。SLAはあくまでもコストと品質を最適化するための道具である。“魔法の杖”ではない。準備段階や導入後の努力を怠ると、かえって害をもたらす。
続きは日経コンピュータ2003年4月7日号をお読み下さい。この号のご購入はバックナンバー、または日経コンピュータの定期ご購読をご利用ください。





















































