情報システムの運用部門が、主役を張る時がやってきた。運用部門こそがシステムを駆使し経営に貢献する役割を担える。第1に、既存システムの有効活用を後押しできる。利用部門にもっとも近い位置にあり、業務の流れを熟知しているからだ。第2に、使われていない情報システムを再評価し、使い込んでいける。むやみに新システムを作るより、経営に多くの利点をもたらす。運用部門は主役を張るために、自身の業務プロセスを見直すとともに、開発部門や利用部門・経営者と密なコミュニケーションをとるべきである。
本記事は日経コンピュータ2002年11月18日号からの抜粋です。そのため図や表が一部割愛されていることをあらかじめご了承ください。なお本号のご購入はバックナンバー、または日経コンピュータの定期ご購読をご利用ください。
「情報システムの運用部門は、単なるオペレータ集団ではない。運用部門は、企業内でシステムの有効活用に貢献できる存在である。このことを強く思うようになったのは、かつて私が自動車メーカーの情報システム部門に在籍していたときだ。注文生産品を管理するシステムを利用して納期順守率を上げていこうと、製造・検査・物流といった各部門の担当者が集まり、納期順守率の向上に取り組んだ。そのプロジェクトはそれなりの効果をあげた。しかしプロジェクトが解散したあと、継続した効果は得られなかったようだ」。
「そこで思ったのは、長年にわたりシステムの利用効果を低減させないようにするため、常に利用効果を監視する部門が必要だということだ。この役を引き受けられるのは運用部門しかないと思っている。システムを常に管理しているし、利用部門と接点があるからだ」。
運用支援ソフトを販売するビーエスピーの桂元親専務は、運用部門の価値を説いてやまない。約30年間、情報システム部門に在籍し、運用部門の重要性に気付いた桂専務はビーエスピーに転職。「開発は一時だが運用は一生続く。システムを安定稼働させるのは運用部門の目的ではなく手段。稼働するシステムをどう生かしていくかに取り組むべきだ」と力説する。
さらに桂専務は、「利用部門の要請があるとはいえ、情報システム部門が毎年新システムを次々に開発しているのはおかしくないか。古いシステムやデータであっても、まだまだ使える部分もあるはず。運用部門が既存システムを評価し直し、もっともっと使いこなせれば、経営へ貢献するところは大きい。逆にシステムを開発するだけでは、保有するシステム全体がどんどん肥大化してしまう」と指摘する。
企業が抱える情報システムを、古時計に例えてみよう。長年使ってきただけに、表面はいささか汚れているかもしれない。しかし、定期的に手入れをし、部品を交換して、ネジをしっかりまいてやれば、まだまだ使える。「運用部門こそ“主役”」とは、古時計にネジをまく重要な役割という意味である。もちろん、古時計を捨てて最新のブランド物デジタル時計に買い換える手もあるだろう。ただし金がかかるし、なにより利用者が新しい時計になじめるかどうかわからない。
運用は最上流工程である
古時計を修理する場合、修理そのものは時計を作った人に依頼することになる。どの部品をどう直すかを依頼する役割も、ネジを預かる運用部門が担うべきだ。極論すれば、「運用部門が開発部門をコントロールする必要がある」(日本IBMの福島義英ITコンサルティング シニアコンサルタント)。
福島氏も桂専務と同様に運用部門への思い入れが極めて強い。「情報システムに関する業務の中で、システムの運用こそが最上流工程である。したがって、運用部門はそれにふさわしい権限と責任、そしてスキルを持つべきだ。経営に貢献できる、品質が高く運用しやすいシステムを開発するために、運用部門がシステム開発部門にあえて物申す必要がある」。
福島氏は10数年間にわたり、日本IBMの情報システム部門に在籍し、社内システムの運用を担当してきた。それだけに運用現場の苦労は知り尽くしている。「どこの企業もそうだろうが、どうしても開発部門のほうが声が大きい。開発部門と運用部門がケンカをすると、必ず運用部門が負ける。利用部門が求めているシステムを作るのは開発部門だから、最後は運用部門が折れないといけない。といって、いつもケンカに一方的に負けていては、モラールも上がらず、きちんとした運用ができないおそれがある」。
開発部門に一矢を報いたいと考えた福島氏が出した結論は、「サービス責任の宣言」であった。運用部門が「システム運用についてサービス責任を負います」と、社内の他部門に宣言しようというのである。運用の担当部門なのだから、当たり前の話のように聞こえる。
しかし実態は違う。企業の中にあって、運用部門は縁の下の力持ちであり、なかなかその存在が見えにくい。「運用部門の存在が目立つのは、システムをダウンさせたときくらい」(福島氏)。残念なことにこれが多くの企業の実態だろう。
「運用しにくいシステムを黙って動かしていても、その努力は経営者や利用部門からは見えない。障害がひとたび発生すれば、運用部門が経営者や利用部門から怒られる。それなら、『システム運用に関する責任を一手に引き受け、運用部門全体で最善の対策を講じる』という気概を持って、改革に挑んではどうか。生意気なことを言うな、と怒られるかもしれないが、どっちにしても怒られるなら前向きなことをしたほうがいい」。福島氏は、顧客企業を訪問してはこう呼びかけている。
運用部門を削減してはならない
運用部門が経営者や利用部門に対して、「責任を持ってシステムを運用します。ですから必要な権限と資源を下さい」と改めて要請する。そのかわり、きっちりと運用サービス責任を果たせる組織や運用プロセスを確立し、開発部門はもちろん、利用部門や経営部門ともコミュニケーションをよくしていく。
こうした努力を継続すれば、運用に関する投資案件の重要性を経営者や利用部門に理解してもらえる可能性が高まっていく。「利用部門の強力な後押しがあれば、サービス責任を負うための資源を獲得しやすくなる」(福島氏)。
運用のために前向きな投資を会社にしてもらおう、という指摘は重要である。「運用部門が経営陣に対して、『これだけコストをかければ、これだけのことができる』と理詰めで説明しないと、予算を勝ち取ることはできない」と、運用管理ソフトを販売するBMCソフトウェアの松本浩彰ソリューションアーキテクトは指摘する。厳しい経営環境の中、運用部門は真っ先にコスト削減の対象になりかねないからだ。「現在、運用業務について費用対効果を測定している運用部門は少ないのではないか。不景気だからこそ、運用サービスにかかる固定費がなぜ必要なのかを、明確に説明できるようにしておくことが重要だ」(松本氏)。
経営者が金の卵を産む運用部門を単なるオペレータ集団と誤認し、人数を減らすことに汲々としていては、経営に貢献できるシステムなど絵空事に終わってしまう。「今や“システム運用イコール経営”。システム運用を重視しなければ、ビジネスそのものの信頼性を確保できない」(富士通総研の福浩邦マネジングコンサルタント)。こういう時代において、運用をコスト削減の対象と見ること自体がそもそも誤っているのである。
| 運用改革に挑んだ 3社の奮戦記 |
企業のシステム運用部門の業務改革が急務である。運用部門内でこれまで続けてきた運用プロセスそのものを見直す。運用しやすいシステムを引き受けられるよう、システム設計段階から運用部門が積極的に参加する。利用部門と密接なコミュニケーションを取ることも欠かせない。システム運用部門を強化する努力を続けてきた荏原製作所、東京海上システム開発、ヴィンキュラム ジャパンの取り組みを紹介する。
プロセス改善でリスクを回避
荏原製作所、東京海上システム開発
「これからは運用部門が責任を持ってオープン系システムを引き受けます!」――。今年9月30日、荏原製作所情報・通信本部IT事業センターの大河内 哲郎 副事業センター長は、運用サービスに関する説明会の場でこう宣言した。説明会には、荏原製作所の情報・通信本部所属の約50人が参加していた。大河内副事業センター長は、荏原製作所のシステム運用を担当する運用サービス室の室長を兼務している。
この宣言は、大河内氏が運用部門の改革を社内にアピールするためのものだった。「4月からの6カ月間、運用体制の見直しを精力的に進めた。その結果、我々はメインフレームだけでなく、オープン系システムも、責任を持って引き受ける自信を持つことができた」と大河内氏は語る。「システム運用を任せられる部門は我々のほかにはいないという強い意志をもって宣言した」。
荏原製作所の運用部門はこれまで、社内で稼働する約170台のオープン系サーバーのうち、2割程度しか管理していなかった。残りは、開発部門が運用していた。運用部門に所属する約50人はおもに、メインフレーム上のアプリケーションの運用業務に従事していた。
今後は、これまで開発部門が担当している8割のオープン系システムを順次引き継げるようにする。9月から引継ぎを始めて来年3月までには、荏原製作所の事業部や関連会社で利用する20システムの引継ぎを済ませる予定だ。「システムの中には運用手順書が整っておらず、すぐに引き継ぐのは難しいものもある。開発部門の協力を仰ぎながら引継ぎを順次進めていく」と大河内氏は語る。
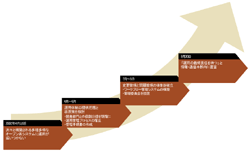 |
| 図1●荏原製作所 情報・通信本部IT事業センター運用サービス室が進めた運用改革の経緯 |
6カ月の取り組みで運用部門が変貌
運用部門が管理するサーバーの台数が限られていたことにはいくつかの理由があった。システムを新規稼働させるにあたって、開発部門から運用部門へシステムを引き継ぐ体制があいまいだった。オープン系システムを開発するときのハードやOS、ミドルウエアの選定は、開発部門に任せていた。さらに運用部門が開発段階のシステム設計に強く関与していなかった。「さまざまなプラットフォームのオープン系システムが混在してしまい運用部門の技術修得が追いつかなかった」(大河内氏)。
大河内氏が情報・通信本部の運用部門の業務改革に着手したのは、昨年4月から。大河内氏の業務改革の手腕を見込んだ情報・通信本部長からの要請を受けて改革を担当することになった。大河内氏は、荏原製作所の賃金制度の大幅見直しをやり遂げた経験を持つ、根っからの業務改革屋である。
大河内氏はまず昨年4月から2カ月かけて運用業務の課題を洗い出した。「課題が多すぎて、どれから着手してよいのかわからなかった」(大河内氏)。運用手順書の作成やドキュメント管理、引継ぎ手順の確立とやるべきことは山積していた。結局、問題の洗い出しの終わったあと、手詰まりの状態で今年を迎えてしまった。「ある開発担当者から『いったい運用部門は何をしてくれるというんだ』と言われた。この言葉がグサリときた」と大河内氏は振り返る。「何とかしなければ」。大河内氏はある決断をした。
システム変更と障害管理の改革から着手
その決断とは、「今年4月から3カ月で、運用改革の方針を示し、そのあとの3カ月で必ず結果を出す」ことであった(図1[拡大表示])。運用部門内から「そのような短期間では、あまりにも無茶だ」という声が上がった。しかし、「期限を定めなければいつまでたっても運用部門が進むべき方向は定まらない」と大河内氏は答えた。改革に先立ち、運用部門の役割を「信頼性や可用性、安全性に責任を持って運用サービスを提供する」と定義。さらに、「今後、2年かけて業界トップ水準の運用体制を整える」という運用部門内の目標を掲げた。
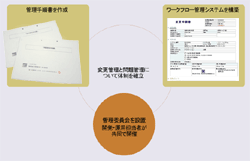 |
| 図2●荏原製作所 運用サービス室が今年4月から9月にかけて整備したシステム管理体制。既に稼働する一つのサーバー・システムを対象に進めた |
打ち出した方針は、「システムの変更を管理する体制と、障害発生時の問題を管理する体制の二つに絞って整備する」ことだった。「いずれも日々の業務の課題となっており、最優先で解決する必要があった」と、大河内氏は説明する。改革方針が固まったのち、変更や問題が発生したときの業務プロセスを手順書の形にまとめた(図2[拡大表示])。例えば、システムの変更をする場合、障害が発生したあとで、元の状態に戻せるかどうか、以前に同様の変更作業をしたことがあるかなどをチェックするようにした。
今年7月から実際の管理体制作りに着手した。荏原製作所の品川事業所で稼働する、プラント開発部門の業務システムを対象に運用部門の4人が中心となって改革に挑んだ。手順を徹底させるために、手順書に基づいたワークフロー管理システムをノーツで開発した。
システム全体への影響が大きい変更案件で、手順書が整っていないものは、開発部門と運用部門の担当者が、変更管理委員会を開いて、変更できるかどうかを検討することにした。
問題管理でも専門の委員会を設けてシステム障害に対処する。問題管理用のワークフロー管理システムも10月下旬に完成させた。今後は他のシステムについて、変更管理や問題管理の体制を整えていく。「今回まとめた管理手順の9割は他のシステムにも流用できる」と大河内氏はみている。
運用部門は、変更管理や問題管理のほかに、新規開発案件を対象とした運用設計基準書をまとめた。運用部門が一連の取り組みを進めていくうちに、開発部門の担当者から「運用部門は変わった」という評価を受けるようになったという。
さらに運用部門と開発部門の間で、コミュニケーションを取り合うようになった。「これまで開発部門から、新規の開発案件で運用面での相談を受けることはほとんどなかった。開発部門から相談があるのは、非常にうれしい」と大河内氏は徐々に出つつある改革の成果に顔をほころばせる。
続きは日経コンピュータ2002年11月18日号をお読み下さい。この号のご購入はバックナンバー、または日経コンピュータの定期ご購読をご利用ください。
取材を通して印象に残ったのは、「部員の士気をどう高く維持していくか」に腐心している運用部門の責任者が多かったことです。士気向上のため、「運用業務に固定することなく、必要に応じて開発業務も担当してもらう」、「メインフレーム運用だけでなく、オープン系システムの運用も担当し、スキルを磨いてもらう」、「運用業務の状況を社内に公開して自らの取り組みをアピールする」といった策を講じている企業がありました。
「さまざまなシステムを運用する」、「運用だけでなく開発も担当する」といった仕組みを用意することは、スキルアップを重視する若手社員の士気に大きな効果がありそうです。以前、電車の中でSEらしき二人が、「システム運用ってスキルが身につかないみたいだね」、「うーんそうだなあ」という話をしているのを耳にしたことがあります。
スキルアップの道を運用部門にも用意しておけば、この二人が運用を担当することになっても、「この前話したことはどうやら誤解だったようだ」と思い直すことでしょう。(西村)





















































