「インターネット時代を切り開いた科学者がノーベル賞を受賞」。ニューヨーク・タイムス紙の見出しである。
今年のノーベル物理学賞は,IC(集積回路)の発明者であるJack S. Kilby(1958年当時の写真:米Texas Instruments提供)をはじめ,電子部品の基礎研究・開発に取り組んだ3人の科学者に授与された。彼らの発明・研究は,コンピュータや半導体レーザーなど現在のIT社会の基盤を支えている。間違いなく偉大な業績である。先のニューヨーク・タイムス紙の見出しは,それをたたえたものだ。
化学賞を受賞した白川英樹筑波大学名誉教授らの研究も,導電性プラスチックに関するもの。エレクトロニクス分野での実用化に直結するという点で物理学賞と共通する部分が多い。スウェーデン王立科学アカデミー周辺で,「今年の物理・化学賞は,実用科学に大きく傾いた」とささやかれているのも納得できる。
近年のノーベル物理学賞は,「新素粒子の発見」や「物質の相転移」など基礎科学の研究に対して授与されるケースが多かったが,今年はそうした傾向が一変した。基礎研究に携わる科学者のなかには,「今年の受賞者の成果は科学ではなく,技術に近い」と不快感を露にする人もいるという。
受賞したKilby氏自身も,ニューヨーク・タイムス紙とのインタビューのなかで,「私は自分の業績を『工学的成果』だと認識している。(科学成果に与えられるはずの)ノーベル賞受賞は意外だった」と述べている。
しかし科学と工学は日々,現代社会への影響力を強めている。その成果が日常生活でどのように応用されるのか,素人にも理解できる点で今年の授賞傾向はむしろ歓迎すべきだと,筆者は考える。これによって今後ますます,理学と工学の接点に注目が集まるだろう。
さて今回のコラムでは,せっかくIC発明者の業績に触れる機会を得たこともあり,過去にさかのぼって現在のIT時代の根幹をなす電子・情報工学の発展史を簡単に紹介してみたい。まずはトランジスタの発明から始めよう(量子物理学の誕生から始める手もあるが,残念だが筆者の手に余る)。
ベル研究所の科学者だったJon Barden,Walter Brattain,William Shockleyの3人が,トランジスタを開発したのは1947年のことだった(ちなみに3氏ともノーベル賞を受賞している)。発明の端緒となる科学的発見をしたのがBardenとBrattainの2人。彼らの実験成果に量子物理学的な解釈を与え,トランジスタの理論を構築したのがShockleyだ。トランジスタの価値を熟知していたShockleyは,その商用化を目指して1956年に自ら会社を設立し,全米の有能な科学者を集めた。
Shockleyは天才であると同時にかなり変わった科学者だった。せっかく集めた優秀な科学者たちが,「自分(Shockley)の研究成果を盗み,破壊しようとしている」という奇妙な妄想を抱いた彼は,研究員全員を嘘発見器にかけるなど,厳重な管理体制を敷いた。これに耐え切れなくなった若い科学者は,Shockleyの研究所を退社してFairchild Semiconductorという会社を興し,トランジスタの研究開発を続けた。このなかには,後にFairchild社を離れ,1968年に米Intelを創業したRobert NoyceやGordon Mooreも含まれていた。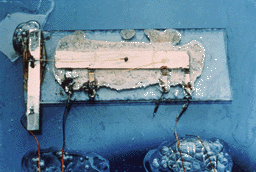
若手に見捨てられたShockleyは,ますます独自の世界に閉じこもってしまい,1960年代以降は学界で真面目に相手にされなくなる。ちなみに白人至上主義者と言われたShockleyは,実は日本人科学者の業績を真っ先に認めるという「確かな眼」ももっていた。
江崎玲於奈が発明したエサキ・ダイオードの価値を発見したのは,紛れもなくShockleyである。江崎は1957年に,ソニーの前身である東京通信工業の研究室でエサキ・ダイオードを発明し,日本物理学会に発表した。しかし,反応は芳しくなかった。Shockleyは1958年にブリュッセルで開催された国際会議で,エサキ・ダイオードの価値を力説し,これによって江崎玲於奈の名前と研究成果は世界中にとどろいた。
トランジスタの実用的価値を最大限に引き出したのは,Shockleyの研究所を飛び出したRobert Noyceと,彼のライバルで米Texas Instruments(TI)のエンジニアだったJack Kilbyである。2人は1958年に,それぞれ独自に集積回路(IC)の開発に成功した(写真::米Texas Instruments提供)。ICとは,複数のトランジスタとそれらを結ぶ配線を,シリコン基板上に形成したものである。今日まで続く果てしない小型・集積化の競争が,このときに始まった。
さてICの発明では,Kilbyの方がNoyceよりも半年先んじた。しかし,性能や使い勝手ではNoyceのICが勝っていた。Kilbyが基板にゲルマニウムを採用したのに対し,Noyceは今日でも主流のシリコンを採用した点でも両者は異なっていた。結局,2人は別々の特許を取得することになる。ちなみにNoyceは1990年に他界したが,生きていればKilbyとノーベル賞を分け合っただろうといわれている。またTI社の持つ「Kilby特許(いわゆる275特許)」は,1980年代に日本をはじめとした世界各国の半導体メーカーにとって大きな影響を及ぼすことになる。
さてNoyceとKilbyが発明したICは,現在のパソコンの記憶をつかさどるメモリや頭脳の役割を担うマイクロプロセサへとつながっていく。このマイクロプロセサの開発に日本人技術者が加わっていたことは,良く知られた事実である。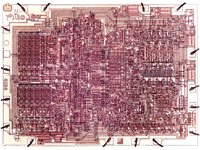
マイクロプロセサの発明者に名を連ねるのは,日本の電卓メーカー「ビジコン」のエンジニアだった嶋正利である。嶋はIntel社のエンジニアとともに,マイクロプロセサの開発に取り組んだ(正確にはビジコンの電卓向けのプロセサ)。自分が勤める会社が発注した製品を,Intel社のTed HoffやStan Mazor,Federico Fagginらとともに開発したのである。世界初のマイクロプロセサ「4004(写真:提供Intel)」は,こうして1971年に完成した(ちなみに最初の4004には嶋の家紋が入っている)。その後,嶋はIntel社に引きぬかれ,8080などベストセラーのマイクロプロセサの開発を手掛けることになる。
4004の外形寸法は3mm×4mmだった。そこに2300個のトランジスタを集積していた。その後集積度は飛躍的に高まり,Intel社が開発中のPentium 4プロセサでは4200万個のトランジスタを集積する。
Kilbyはノーベル賞を受賞した直後にインターネットで公表した手記のなかで,「集積回路の限界と半導体技術の死が最近取り沙汰されている。しかし,これは不当に誇張された見方である。技術者は今後とも限界を突破し,集積度はますます向上するだろう」と強気な見解を発表している。「ITは不滅」ということだろうか。(本文中,敬称略)
(小林雅一=ジャーナリスト,ニューヨーク在住,masakobayashi@netzero.net)





















































