2003年3月12日。米Intelはノート・パソコン用の新CPU「Pentium M」を発表,同時にこのCPUを搭載したノート・パソコンをメーカー13社が披露した。発表会でこれらのパソコンを眺めながら,筆者は何となく裏切られたような違和感を感じていた。どの製品も筆者が期待していたものとは違うパソコンだったからだ。
前評判は「低消費電力」だった
この記事の主役,Pentium Mは発表になったばかりなので,「そもそもPentium Mって何?」という方もいらっしゃるだろう。でも「Banias」と聞けば,省電力を狙った「IntelのCrusoe対抗CPU」として見聞きしたことがある方も多いのではないだろうか(関連記事)。Baniasの正式名がPentium Mである。
だが,3月12日のIntel社の発表で前面に押し出されたのは,CPU,チップセット,無線LAN機能などの総称である「Centrino」というブランド名(関連記事)。Pentium MはCentrinoで使われるCPUなのである。Intel社はブランド名を前面に出して,CPU名を後ろに追いやってしまった。これについての論議は機会を改めて,別の日経バイトの記者が執筆する予定である。
そもそも筆者はなぜPentium Mに期待を寄せていたのか? 1つにはPentium MがIntel社としては初めて,ノート・パソコン用にCPUコアから設計したCPUである点が挙げられる。Intel社のノート・パソコン用CPUは「386SL」から「モバイルPentium 4-M」まで何製品もある。これらは,既存のCPUコアを流用してノート・パソコン用に仕立てた製品だった。
Pentium Mは,米Transmetaのノート・パソコン用CPU,Crusoeへの対抗策として開発された。新しく開発したCPUコアで,動作周波数(いわゆるクロック数)当たりの実行効率(Instructions Per Clock cycle)をPentium III以上に高めた。このため動作周波数をもってして,既存のCPUと比較することはできなくなっている。さらに,動作周波数と電源電圧を多段階に切り替える「拡張版Intel SpeedStep」と,使っていないユニットの電力をカットする機構を搭載した。これらにより,システムの負荷に応じて無駄な電力をカットすることで,低発熱・低消費電力を実現する。
つまり,Pentium Mを使うと,電池が長持ちするノート・パソコンが作れると考えられていたわけで,筆者もその1人だった。大きく重い拡張バッテリを付けなくても,新幹線での東京-大阪往復くらいはへっちゃらなノート・パソコンが出てくるのでないかと。
予想以上に高速だったPentium M搭載機
ところがIntel社の発表会で並んだ新ノート・パソコンのスペックを見ると,そうでもないようだ。実際にどうなのか? 試作機で簡単なベンチマークをした。試用できたのはNECのA4ノート「LaVie M LM500/5D」(重さは約2.1kg)とソニーの「バイオU PCG-U101」(同880g)だ。CPUはLM500/5DがPentium M 1.3GHz,ソニーのPCG-U101がPentium Mコアの超低電圧版モバイルCeleron 600A MHzである。
日経バイト2003年4月号の締め切り直前に,NECとソニーから試作機を借りることができた。この2台のべンチマーク・テストの結果は日経バイト2003年4月号(3月22日発行)に掲載するが,そこで得たPentium Mに対する感想は「予想以上に速い!」というものだ。Pentium Mコアの超低電圧版モバイルCeleron 600A MHzでさえ,体感速度はかなり速い。
その一方で,「でも・・・バッテリの持ちはそれほど延びてはいないな」という印象も残った。ユーザーの環境にもよるが,Pentium M搭載機は1時間程度しかバッテリ駆動時間が延びなかったからだ。このバッテリ駆動時間は,それを重視するユーザーにはまだまだ物足りない水準だ。松下電器産業のモバイルPentium III-M 933MHz搭載機の「Let's note LIGHT」が5時間に達することを考えると,バッテリ駆動時間を重視してPentium M搭載機を選ぶケースはないように思える。
そこで,はたと気づいた。そもそもPentium M搭載機の第一陣は,長寿命ではなく高性能指向なのではないか,ということだ。筆者は薄型で軽量,標準バッテリでも実働で5時間を優に超え,8時間は動作するノート・パソコンをどこかで期待していた。Pentium M搭載機の東芝「DynaBook V7」のバッテリ駆動時間はメーカー公称値で6.8時間。ただ重さは3.3kgと持ち歩くにはややつらい。
各社のPentium M搭載機を見渡してみると,いずれもグラフィックス・チップは外付けだ。チップセットにグラフィックス・コアを内蔵するPentium M向けチップセット「Intel 855GM」を採用したメーカーはない。各社の説明を総合すると「855GMの出荷時期が開発スケジュールと合わなかった」という事情によるところが大きいようだ。
Pentium Mの余力でグラフィックス性能を向上
結果として,Pentium M搭載機の第一陣は,Pentium Mによって生まれた電力と熱設計の余裕で,高性能グラフィックス・チップを搭載した格好になる。グラフィックス・チップも性能が上がれば,電力は消費するし,熱も発生する。パソコンを自作している方ならご存じだろうが,高性能グラフィックス・チップを搭載したグラフィックス・ボードは,ボード上にファンを搭載して,空冷で熱を逃がしているほどなのだ。
今までのノート・パソコンでは,CPU自体が電力を使い,発熱もするので,高性能なグラフィックス・チップを搭載できなかった。ところが,低消費電力・低発熱のPentium Mならば,バッテリ駆動時間をそこそこに抑えれば,高性能グラフィックス・チップを搭載できる。バッテリ駆動時間を追求せずに,高性能グラフィックス・チップを搭載してシステム全体としての性能向上を図る――このようなデザイン方針で生まれてきたのが,第一陣のPentium M搭載ノート・パソコンだと理解できるのである。
これは前述の筆書が期待していたPentium M搭載ノート・パソコンとは違うものだ。期待が「はずれた」と言わない。今までのノート・パソコンを凌駕する立派な性能を出すからである。だが,期待とは違っていたことは確かである。
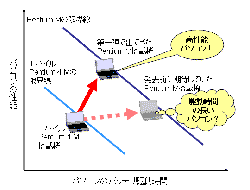 この期待違いを図1[拡大表示]にしてみた。横軸がバッテリ駆動時間で,右に寄るほどバッテリ駆動時間は長くなる。縦軸はパソコンの性能で,上ほど性能は高い。あるCPUを使っている以上は,バッテリ駆動時間とパソコンの性能はトレードオフの関係にある。つまり,パソコンの性能を上げようとすると,バッテリ駆動時間は短くなるし,逆にバッテリ駆動時間を長くしようとするとパソコンの性能は抑えざるを得ない。バッテリ駆動時間と性能の二兎を同時に追うことはできないのである。
この期待違いを図1[拡大表示]にしてみた。横軸がバッテリ駆動時間で,右に寄るほどバッテリ駆動時間は長くなる。縦軸はパソコンの性能で,上ほど性能は高い。あるCPUを使っている以上は,バッテリ駆動時間とパソコンの性能はトレードオフの関係にある。つまり,パソコンの性能を上げようとすると,バッテリ駆動時間は短くなるし,逆にバッテリ駆動時間を長くしようとするとパソコンの性能は抑えざるを得ない。バッテリ駆動時間と性能の二兎を同時に追うことはできないのである。
ある駆動時間における最高性能の点を連ねていくと,線ができる。これを「限界線」と呼ぼう。この限界線よりも上あるいは右のパソコンは作れない。現実的には,限界線が直線になるのか曲線になるのか分からないが,ここではあくまでモデルとして直線で表した。
これまでの最速のノート・パソコン用CPU「モバイルPentium 4-M」の限界線を水色で示した。パソコンの設計者は,この限界線上あるいは左下上のどこかで,バッテリ駆動時間と性能の折り合いを付けて,製品化を図る。ほどほどの駆動時間を確保すると,ほどほどの性能にしかならなかった。
Pentium Mが出てきたことによって,限界線は右上にシフトする。図では青の線だ。筆者は図中,右のパソコンのように,これまでのノート・パソコンよりも性能向上はそこそこだが,ぐんとバッテリ駆動時間が延びた長持ちバッテリ・ノートを期待していたのである。ところが実際に第一陣で出てきたパソコンは,すでに述べたように駆動時間の増加はほどほどで,ぐんと性能を上げたパソコンだった。
Pentium Mが広げる“デザイン”の幅
このバッテリ駆動時間と性能のトレードオフの図を用いると,Pentium Mがノート・パソコンの“デザイン”の幅を広げたということも,理解しやすいと思う。ここでいうデザインは,物理的な形状のことではなく,各要素をどのようにバランスさせるかということである。設計といっても良いかもしれない。
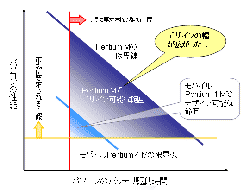 このトレードオフの図に,X軸に平行な市場に要求される最低限の性能の線,Y軸に平行な市場に要求される最低限のバッテリ駆動時間の線を加えよう(図2[拡大表示])。どちらの線もある時点においての,ということである。時間が経つにつれ,市場に要求される性能は上がるし,駆動時間は延びる。すなわち,前者は上に,後者は右にシフトしていく。しかし,製品化時期が決まれば,最低限のラインは決まる。
このトレードオフの図に,X軸に平行な市場に要求される最低限の性能の線,Y軸に平行な市場に要求される最低限のバッテリ駆動時間の線を加えよう(図2[拡大表示])。どちらの線もある時点においての,ということである。時間が経つにつれ,市場に要求される性能は上がるし,駆動時間は延びる。すなわち,前者は上に,後者は右にシフトしていく。しかし,製品化時期が決まれば,最低限のラインは決まる。
ここで,モバイルPentium 4-Mを使ってノート・パソコンをデザインしようとすると,同CPUの限界線と,最低限の性能の線,最低限のバッテリ駆動時間の線で囲まれた三角形のエリアが,デザイン可能な領域となる。Transmeta社のCrusoeを使うと,限界線はもっと横に寝たものになり,ほどほどの性能で,バッテリ駆動時間の長いノート・パソコンをデザインできる。
ところが,限界線が右上方にシフトした,Pentium Mを用いれば,三角形の面積は広がる。つまりパソコンのデザインの幅が広がるというわけである。
これまではバッテリ駆動時間を確保するために,ノート・パソコンの仕様の取捨選択の幅が狭かった。高性能のCPUを使おうとすれば,消費電力が上がりきょう体を大きくせざるを得ない。といって省電力のCPUを採用しようとすれば,Crusoe程度しか選択肢はなかった。
グラフィックス・チップの消費電力を減らそうとチップセット内蔵のグラフィックス機構を使うと,ビデオ・メモリーはメイン・メモリーと共有になり,OSで実際に使える容量は減ってしまう。これにコストと実装面積という要素が重なる。メーカーはそれぞれの最適解を出すために苦労を重ねてきた。Pentium Mという選択肢が増えたことで,パソコン・メーカーとしては性能を上げることもバッテリを長持ちさせることを目指すことも両方できるようになったというわけだ。
第二陣はバッテリ駆動時間の長いノートに期待
性能と駆動時間の両方を高めた好例は,試作機を評価できたソニーの新バイオUだ。必要十分な処理速度を確保しながら,バッテリ駆動時間も3.5~5時間を確保している。筆者はPCG-U101のポインティング・デバイス周りの練り込まれた操作性(キー・ピッチは狭いがそれは見切った)に目を見張った。直射日光下でも視認できる半透過型の液晶パネルもモバイルでは魅力的に写る。筆者の購入をためらわせるのは,もはや資金面の事情だけである。
Pentium-Mでは,性能と駆動時間の両方を追求するのではなく,性能を控えめにしてバッテリ駆動時間をぐっと伸ばしたノートを作るという自由度もあるわけだ。発表前に筆者が期待していたノート・パソコン像である。
具体的には,いわゆるミニノートと呼ばれる小型ノート・パソコンに期待したい。ミニノートでは,従来のバイオUと同じく,きょう体の大きさと熱設計,バッテリ駆動時間といった制約から,米Transmeta社の省電力CPU「Crusoe」シリーズを採用することが多かった。ソニーのバイオC1,東芝のLibrettoや富士通のLOOXシリーズなどである。
筆者は,上記のあるミニノートのユーザーだが「最新のパソコンがここまで遅いのか」と半ばあきれたことがある。Webブラウザ一つ立ち上げるのに優に5秒はかかるのだ。それでも携帯性を重視して購入に踏み切った。購入後にまずやったのは,OSの入れ替えと各種の設定。実用的な体感速度にまでチューニングすることだった。
Transmeta社も次期CPU「TM8000」を2003年第三四半期に量産出荷する予定だ。ただ今手にはいるパソコン向け高性能・省電力CPUはPentium Mしかない。夏商戦には,グラフィックス・チップを取り込んだチップ・セット855GMを搭載して,軽くてバッテリの持ちがいい,第一陣とは異なる傾向のPentium M搭載機が姿を現すはずである。
もっとも筆者は夏まで待てるかどうか。とあるメーカーの直販サイトを訪れては,妻にどう言い訳をしようかと考えてブラウザを閉じる,という動作が日課になってしまった今日このごろなのである。
(高橋 秀和=日経バイト)





















































