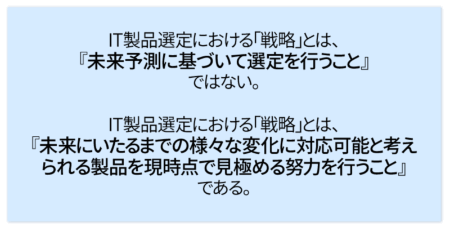前回は、クラウド導入で散見される「スモールスタート」には注意が必要であること、「戦略なき迅速」は「拙速」に他ならず、後に大きな問題を引き起こす可能性が高いことを述べた。今回は、クラウドを含むIT製品の選定における「戦略」について解説する。なお、本連載における「製品」とは、ハードウエア、パッケージソフトウエア、サービスなど、ベンダーから販売されているIT製品やサービス全般のことを指している。
そもそも「戦略」とはどういう意味だろうか。元々は戦争用語であり、戦いに勝つために様々な戦闘を組み合わせることを「戦略」と呼んでいた。20世紀になってからは「経営戦略」に対する研究が進み、ビジネスで勝ち抜くための基本方針、ガイドライン、基本設計図を「戦略」と捉えることが多くなった。それでは、IT製品選定における「戦略」とは何かということについて考えてみよう。
IT製品選定に未来予測は必要か
ITアナリストである筆者は、ITの「未来予測」を求められることが多い。しかし、それは非常に困難な作業である。例えば、10年前(2005年)にAWS(Amazon Web Services)やFacebookの現在の隆盛を予測できた人はいないだろう(Facebookの創業は2004年、AWSのサービス開始は2006年である)。
IT製品選定における「戦略」は「未来予測」のことではない。未来は不確定で予測不可能だが、未来にいたるまでの様々な変化に対応可能と考えられる製品を現時点で見極める努力を行うことは可能であり、極めて重要な活動である。このような活動がIT製品選定における「戦略」なのである。