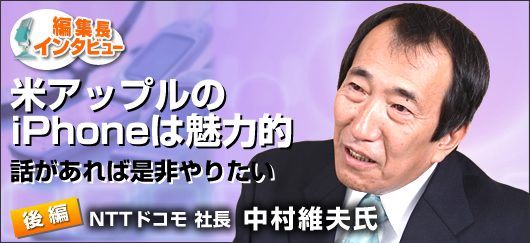
MVNOも大きなテーマだ。
MVNOはサービスから得る収入と,当社から借りた回線料金との差額で儲ける必要がある。しかも,端末や料金を安くしなければユーザーには受け入れられない。こうした構造の中でビジネスを展開する必要があるので,よほど魅力的な端末やサービスでなければMVNOのビジネスは成り立たない。例えば米アップルが2007年1月に発表したiPod搭載の携帯電話機「iPhone」のような特徴がなければ厳しい。
アップルとは交渉しているのか。
 |
| 撮影:細谷 陽二郎 |
交渉はしていない。アップルが日本で参入するかどうかは分からないが,あれだけ人気のある端末なので,話があれば是非やりたい。端末の魅力でユーザーを集めるタイプのMVNOはこれから一番伸びると見ている。
ただ,当社にとってつらいのは東名阪の周波数帯域があまりにも不足していること。MVNOに設備を貸したために当社がパンクすることだけは勘弁してほしい。「新宿や渋谷,池袋では17時台になるとNTTドコモの端末が通じなくなる」といった事態は避けたい。こうなると,本当に貸せなくなる。
特にMVNOが音声定額サービスを提供すると,トラフィックは一気に増える。ネットワークをよほどうまく構築していかなければ立ち行かなくなる。MVNOは周波数帯域の有効活用という意味で有効だが,周波数帯域が不足している現状では大賛成とはなかなか言えない。中でも苦しいのは東京。地方であれば喜んで提供する。
PHSのデータ通信サービス「@FreeD」の後継として,2007年秋ごろからFOMAを利用した64kビット/秒の定額サービスを開始する。さらに高速な定額サービスを投入する予定は。
64kビット/秒にとどまる気はない。2006年8月から下り最大3.6Mビット/秒のHSDPA(high speed downlink packet access)を始めているが,そのあとには第3世代携帯電話(3G)を高度化した「Super3G」(3.9G)が控えている。HSDPAとSuper3Gが優れている点は周波数帯域の使用効率が高いこと。これらの技術を導入,展開していかなければデータの増加に追い付いていけず,いずれネットワークがパンクしてしまう。高速化は必然の流れ。下り最大100Mビット/秒のSuper3Gならパソコン向けの定額サービスも十分実現できる。データ通信サービスはもう定額制しかないと割り切っている。
Super3Gや第4世代携帯電話(4G)の展開はいつころになりそうか。
Super3Gは既に動き始めている。現行の3Gをベースにしているので,既存のネットワークに上乗せしていく形になる。商用化の時期は未定だが,2010年ころを目標にしている。
一方,4Gの展開は世界各国の動向をにらみながらになる。日本だけ早く進めても他の国が採用しなければ意味がない。3Gで懲りたので,4Gは世界と足並みをそろえて進める。あとは設備投資の問題。4Gはネットワークを一から構築する必要があるので,投資対効果を見極めながら展開していくことになる。このほか,1Gビット/秒の通信速度で何をするのかという意見も多いが,この点はこれから詰めていく。いずれにせよ研究開発は絶対に必要で,どんどん進めていく方針だ。
モバイルWiMAXを利用した2.5GHz帯の高速ブロードバンドに参入したいというが,どのような位置付けになるのか。
モバイルWiMAXは1台の基地局でカバーできる範囲が公衆無線LANサービスよりかなり広く,スループットも30Mビット/秒程度出る。ネットワークは新たに構築しなければならないが,構築コストは携帯電話のネットワークより安いはず。携帯とは全く別に,定額サービスを実現できる可能性があるので,魅力的だ。用途はデータ通信を想定している。VoIPを利用した音声通話サービスはまだ分からない。
グループを挙げてNGN(次世代ネットワーク)の構築を進めている。携帯電話のネットワークはどうなっていくのか。
正直,まだはっきりとは見えていない。固定と携帯で制御を一体化するのが理想だ。コスト面で見ても,一本化するのが望ましいが,そこまで先の話となるとまだ誰も分からないのではないだろうか。
だから,まずはサーバー機能までの統合を目指すことで合意している。互いにインタフェースを細部まで合わせていく。その一環として,固定と携帯を融合したFMC(fixed mobile convergence)も出てくるだろう。
>>前編
|
(聞き手は,林 哲史=日経コミュニケーション編集長,取材日:2007年3月6日)





















































