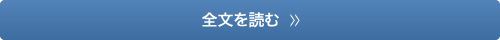今回は、「先が読める人」の6つの特徴のうち、後半の3つについてお話しします。具体的には(4)「図を使って全体像を俯瞰できる」、(5)「具体的に想像することに『こだわり』を持つ」、(6)「発見的に歩める」の3点です。

図を使って全体像を俯瞰(ふかん)できる人
前回、「先が読める人」は「つながり」を意識して情報を読む特徴があるとお話ししました。先が読める人の四番目の特徴は、こうした「つながり」をいくつか「足し算」し、図などを活用し「見える化」することで、部分ではなく全体像を俯瞰できることです。
日本の経済政策の例で、図を使って俯瞰するとはどういうことか考えてみましょう。いま、アベノミクスと言われる景気回復シナリオは、かなりシンプルにいうと次のようなロジックにまとめられます。
このシナリオには、どんな「つながり」が含まれているでしょうか。
つながりのもっとも単純なものは、「原因があって結果がある」という因果関係です。矢印を使って、因果関係を図示し、シナリオのロジックを見てみましょう。矢印の元が原因で、先が結果です。

図にあるように、それぞれの要素間の因果関係が複数存在し、景気回復という「好循環」が生まれる様子がわかります。
このように図にして考えるほうが、言葉だけでロジックを理解するよりもわかりやすく感じませんか。特に、複数の因果関係を考えるときには、図のほうが理解しやすいでしょう。結果、全体像もつかみやすくなるはずです。全体像がつかめるということは、一段高い視点からモノゴトを俯瞰できるようになるということです。
全文はBPnetビズカレッジでご覧いただけます。