調達活動をコミュニケーションの観点で見ると,ユーザー企業とベンダー企業がRFPと提案書という文書をツールとして,企業間のコミュニケーションを図り,両者の利害や思惑が合意できれば契約に進むということである。ただし,それは1対1のコミュニケーションではなく,ユーザー企業(発注側)が1,ベンダー企業(受注側)がn,という1対nのコンペ形式である。
ユーザー側は複数の候補者の中から最適なパートナーを見つけるために,なるべく多くの要求を洗い出し,RFPに記載しようと一生懸命になる。
漏れがあってはいけない。もし漏れがあると,後から「これはRFPに書いてなかったので外しました。別見積もりです」と言われてしまう。また,エンドユーザーから「なんで,これを要求に入れなかったのだ」と文句を言われるかもしれない。こうした理由で,RFP作成時には「とにかくなるべくたくさん詰め込もう。ベンダーはプロだから読めば分かるだろう」と考える。
一方ベンダー側は,競争に勝ち抜かなければ受注できないため,提案書の作成には自ずと力が入る。
競争相手よりも,より良く,より多くの提案を盛り込みたい。自社の提案がどれだけ素晴らしいか,専門的な観点も含めて,より具体的かつ詳細に説明したい。漏れがあってはいけないから少しでも関係する事柄は資料としてはさみ込んでおきたい。
このような受注への熱意が積み重なって,提案書のボリュームはどんどん増えていく。また1枚の紙に詰め込む内容も増大する。重要なポイントはたくさんあり,そのどれも目立たせなくてはいけない。そこで,赤,青,黄色とそれぞれ目立つ色がふんだんに使われていく。そして「これだけ内容が充実していれば,提案書を読めば当社の優位性は一目瞭然だろう」と期待する。
経営者や上司は分厚いRFPを読んでくれない
このような両者の思いから,RFPも提案書も放っておくと,どんどん肥大化し,分厚くなる。枚数が多過ぎ,1枚に内容を詰め込み過ぎ,色を使い過ぎることは,読み手に読んでもらえないRFPの典型である(図3)。
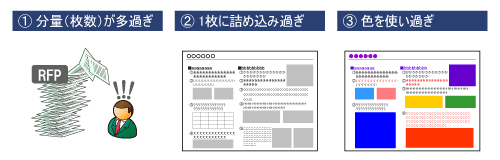
一般的に人間は,あまり過剰な分量の書類を目にすると,とたんに読む気をなくしてしまう。特にユーザー側は,コンペに参加した複数のベンダーから提案書が出てくるので,分厚い提案書をn冊目にすることになる。仮に150ページの提案書が5社から提示されれば750ページである。いくら仕事とはいえ,750ページの全部に目を通すのはしんどい。
もちろん,RFP作成チームの主要メンバーであれば,提案書評価はミッションであるから,頑張って読むはずだ。しかし,上司のマネージャや,さらには最終決定する役員はまず目を通してもらえないだろう。筆者の経験からしても,経営者や上級マネージャはそのような膨大な提案書の山を見ると「すごいね,大変だね,後はよろしくお願いするよ」と逃げてしまうことがほとんどではなかろうか。
これはおそらく,ベンダー側でも同じようなことが起こっていると推測できる。分厚いRFPを受領すると,ベンダーの営業部長やそのラインの担当役員は「すごいRFPが出てきたね。しっかり読み込んで,良い提案ができるよう,頑張りたまえ」と言葉だけ掛けて,中身は読もうともしないのではないだろうか。
RFPと提案書のやり取りがユーザーとベンダーという法人間のコミュニケーションだとすれば,それぞれの担当者レベルだけのやり取りにしか使われないのであれば,十分な効果を発揮するとは言い難い。「労多くて益少なし」となってしまうのだ。担当者レベルだけでなく,上位の管理職,さらには経営者レベルまで含めた多層的なコミュニケーションが行われるべきでる。そして,その多層的な法人間のコミュニケーションが調達活動を成功させ,ひいてはシステム構築プロジェクトを成功させるのである。





















































