創業当初の松下幸之助は苦心して製造した松下式ソケットを手に「どのくらいの価格なら売れるでしょうか?」と販売代理店を回り、意見を聞いては改良していった。「経営学は教えられるが生きた経営は教えるに教えられない。自ら会得するものである」という彼の言葉は、長い間松下経営の基本として語り継がれてきた。こうした幸之助の経営姿勢は、いわゆる現場主義のルーツといってよい。
そして中尾もまた、「対象にぶつかり対象から学ぶ」という現場重視の姿勢を貫いた。会社の規模拡大とともに知識偏重型の社員が増えたが、中尾はモノから教わることの重要性を繰り返し説いた。今回はその中から代表的な四つの言葉を紹介したい。
 |
「新商品の開発は自分の頭で考えるだけでなく、市場から教わる必要がある」と中尾は常に語っていた。松下電器には、1942(昭和17)年に発表された商品づくりの指針があった。それは、「製品には親切味、情味、奥ゆかしさ、ゆとりの多分に含まれたるものを製出し、需要者に喜ばれることを根本的の信念とすること」という全社通達である。「技術の独り歩き」を警鐘する一面を持った言葉でもある。
1970年代初頭、カラーテレビの薄型化競争が激しくなった。ブラウン管の偏向角度を広げていけば大画面が実現できる上、奥行きも短くできる。そこで消費電力の増大や周辺部の画質劣化という原理的欠点を犠牲にしても、国内外のテレビメーカーは大画面を実現すべく広角化を競った。あるメーカーは偏向角度を160度まで広げる研究を進めたほどであった。
 |
| 写真1●90度偏向のクイントリックス管を採用したカラーTVの宣伝広告 「あんた松下さん?」で大ヒットした(「松下電子工業の歩み:1952-1993」より) [画像のクリックで拡大表示] |
松下電器でも久野古夫(元テレビ事業部次長)らが、なんとか110度まで持っていきたいと頑張っていた。これを知った中尾は、「これは邪道だ。単なる技術者の自己満足であり、お客さんにとっては迷惑千万である」と90度で止めるよう指示した。画角を広げるとテレビの消費電力が増大する。お客さんはどんなに大画面だったとしても、消費電力が極端に高いテレビなど望んではいない――中尾は言外にこう指摘した。
そうこうしているうちにオイルショック(1973年)が起こり、省エネ風潮が盛り上がってきた。110度偏向に進みかけていた商品化競争は結局、各社90度に落ち着いたのだった(写真1)。
「技術者の自己満足で仕事をやってはならない。商品というのはお客さんの立場に立って考えるのが本来の姿である」。松下電器の歩んだ道に大きな失敗がなかったのは、このような中尾の地に足のついた考え方に根っこがあるはずだ。
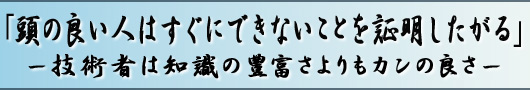 |
昔も今も、知識が豊富だが経験の少ない若手技術者は何でも知識で割り切ろうとする。もちろん知識は大事である。だが、実際の仕事は知識だけでは達成できない。
手を動かしながら身を粉にして熱心に取り組んでいると、そこに新しいアイデアが浮かんでくる。中尾はこう確信していた。つまり、技術者は知識を豊富に持つよりもむしろ感性や直感(カン)が働く方が大切である、というわけである。
どうすればカンが働くようになるだろうか。中尾の教えは次の3点である。
| 常に現場から目を離さず、 現場から情報を得て、 考え抜いては実行を繰り返す。 |





















































