松下幸之助の右腕となったエンジニア、中尾哲二郎。彼は「専門のない専門家」と呼ばれるほど幅広い分野で功績を残した。中尾のモノづくり人生を支えたのは、現場の仕事で練られた「エンジニア哲学」であった。連載第二部では、中尾が後輩らに遺した珠玉の言葉を引きつつ、21世紀の今にも通じるモノづくりの本質に迫る。
「T字型」さらには「π字型」が理想のプロフェッショナル像、と言われて久しいが、技術と経営の専門分化と複雑化が進む現実を前にすると「T字型になるのも精一杯」と挫折感を抱きたくなる。だが、核にある“哲学”さえ身に付ければ、少なくともT字型になれる道筋を見い出したと言えるだろう。
商品に設計者の魂を込める。商品開発に使命感と責任感を見いだす――。
中尾は商品を開発するに当たって、この二つの主義、あるいは行動理念と言うべきものを貫いていた。
 |
中尾をよく知る人にとって、この言葉ほどポピュラーなものはない(図1)。「セットから声が聞こえるはずだ」「モノはじっと見つめていると、向こうからここをこう直してくれと話しかけてくるようになる」「機械から声が聞こえてくるようにならなければ本当に真剣な仕事をしているとはいえない」など、同じことを訴える中尾の言葉は枚挙にいとまがない。商品に魂を込めていた中尾ならではの言葉と言える。
 |
| 図1●中尾を追悼する社内誌(1981年11月号) 中尾を知る幹部が中尾とのエピソードを惜しみなく明かした [画像のクリックで拡大表示] |
相手を死物と思うな、モノと心が通うほど打ち込め。中尾は21世紀を生きる技術者をこう叱咤激励しているようだ。1972(昭和47)年の中央研究所誌「技術」における中尾の寄稿文『最後の決め手は自分への誇り』を読むと、その思いが見て取れる。
『行き詰る。その壁を一歩突き抜けねばならない。しかもなかなかその一歩を突き抜けることが出来ない。まただれもやったことがない、それを初めてやらねばならない立場におかれた場合、だれも知らないものであればあるほど、不安にさいなまれ、そこでやめようかやめまいかと迷ってしまうと思います。これからは、技術が高度化し、開発に長期を要し、ばく大な投資を必要とすることになればなるほど、この一歩がむずかしくなってきます。こういうとき、この不安と孤独に打ち勝っていくには、“これを完成させるのは自分だ”という強い意欲以外にはないと信じています。
そこまでの切迫感で製品開発に取り組むと“もっと熱してほしいんだ”とか“もっと早く冷却してほしいんだ”とかいうように、製品から声が聞こえてくるような気がするものです。そうしてこの苦難を乗り切ったときに、さらに大きな自信と誇りができ、この自信と誇りが次の偉大な仕事ができる原動力になってきます。』(以上原文ママ)
製品から声が聞こえてくるほどに夢中になれる無類の精神力。これは、まさに中尾の技術者魂の現れと言える。
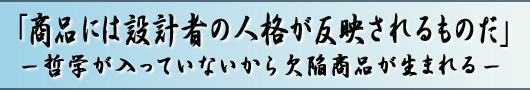 |
1980年代、松下電器産業のモノづくりを変えた手法がある。松下電器の事業部長や関係会社役員を歴任した上田和範が生み出した「RIAL(Redesign and Improvement through Analysis of Line-system)」である。RIALは今風に言えば業務改革を実践するためのフレームワークで、商品開発及び生産システム全体を徹底的に見直すことでムリ・ムダ・ムラを排除し、利益を向上させることを狙ったものである。松下住設機器(現在は社内カンパニーのホームアプライアンス社)など松下グループ企業の現場で成果を上げた。
実はこのRIALには、中尾の「技術哲学」が刻まれている。
1955(昭和30)年、一言居士の若者であった上田は生産機械の設計思想について上司と意見が対立し、とうとう常務の中尾に設計思想の判定を依頼することになった。このとき上田とその上司二人の言い分を平等に聞いた中尾は、「二人で別々に設計してみろ。完成したとき発注者を交えて判定しよう」と命じた。
そのあと中尾の口をついて出た言葉に、上田はハッとした。「上田君、君が設計する機械の図面一枚一枚に君自身の哲学が入っていなければ、それはただの絵にすぎないのだよ」。いたく感銘した上田はそれ以来「入魂の設計」をモットーとした。上田は後に記した著書『RIAL 松下の生産革命』(東洋経済新報社)で、「この教えがRIALに生かされた」と書いている。
RIALのアプローチは、全体を見渡すトータルな視点から、商品の設計思想や生産思想をゼロベースから変えるものだ。その裏には「モノづくりに魂を吹き込む」という中尾の考え方が横たわる。生産のネックになりがちなポイントに焦点を当てて見直しを図る考え方がまだ一般的だった当時としては、画期的なフレームワークだった。
中尾の影響を受けたのは現場の技術者ばかりではない。事業部長などのマネジャクラスも中尾に心を打たれ、彼の哲学を咀嚼(そしゃく)しながらマネジメントに生かしていった。
洗濯機やテレビの事業部長、関係会社の副社長を務めた時実隼太もその一人である。時実の洗濯機事業部長時代、技術本部長だった中尾に新商品の試作品を見てもらう機会があった。商品の背面に回った中尾は、前面から見えない裏蓋のプレス穴にバリ(鋳造品や成型品の加工時に出やすいとがりや出っ張り)が出ているのを見つけた。
「前から見えないといって、バリの出るようなプレスをやってそれを見過ごしているというのは、もうそこに設計者の人格が表れている。こんな商品は品格のある商品とは言えない」と中尾はバッサリ斬った。さらに続けて、「商品にはそこの事業部長の思想が入っていなければならない。思想が入っていないから欠陥商品が生まれるのだ」と時実に向かって忠告した。感じ入った時実はこの忠告に従い、再設計を決めた。
時実はほどなくしてテレビ事業部に移った。試作品の裏蓋を開けてみて雑な配線をしたシャーシを見つけると、「おい、これは品格のある商品とは違うぞ」と設計者にやり直しを命じたという。こうしたマネジャクラスへの啓蒙も、松下電器の良品生産に一役買っていたであろう。





















































