生産性という言葉は,会社の中でも,「生産性が悪い」だとか,「もっと生産性を上げなさい」などと,よく使われる。よく耳にするので,何となく分かった気になっているかもしれないが,その正確な定義は意外と知られていないだろう。
生産性とは,インプットに対するアウトプットの比率である。インプットとは経営資源であり,アウトプットとは付加価値である。
インプットの経営資源は,3通りある。いわゆる,ヒト・モノ・カネである(図1)。具体的には,ヒトについては平均従業員数,モノについては有形固定資産額,カネについては平均総資本額を用い,それぞれ「労働生産性」「設備生産性」「資本生産性」と呼ばれる。
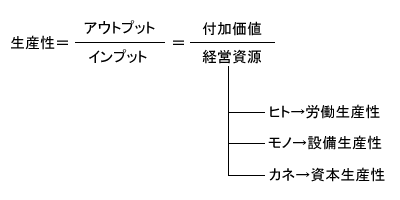 |
| 図1●経営資源はヒト・モノ・カネで構成 |
一方,アウトプットには「付加価値」を用いる。付加価値という言葉も日常的に使われる言葉であるが,その正確な定義は少々難しい。財務分析における付加価値とは,「企業が新たに生み出した価値」と定義される。「新たに生み出した」というところがポイントで,企業が売り上げや在庫という形で生み出した総生産高から,生産のために他から購入したり消費したりした財やサービスを控除した正味の生産高として定義される。
少々難しい言い回しになったが,要するに,100円で仕入れたものを120円で売れるのは,企業がそこに価値を付加したからということだ。たとえば,パソコンが,それを構成している部品代の合計より高いのは,その部品を組み立てることによって,ワープロが打てたりインターネットに接続できたりする新たな価値を付加したからだ。流通業や小売業は,物理的には何も変化させないにも関わらず,仕入額より高い価格で売れるのは,商品に対する入手容易性(アクセサビリティ)という価値を提供しているからだ。もし,流通業・小売業がなかったら,スイス製のミネラルウォーターが欲しい人は,スイスまで行かなければならないのである。
そして,その差額を,企業が付加した価値と考えるというのが「付加価値」である。したがって,近似的に計算するのであれば,付加価値は売上総利益と考えて差し支えないだろう。
行政機関などが付加価値を計算するときは,付加価値の分配面に注目して計算するのが普通である。すなわち,付加価値は,経営資源の提供者に対して対価として分配される。ヒトには人件費,モノには賃借料及び減価償却費,カネには金融費用,国・地方自治体には税金,そして,残った純利益は株主に帰属するという具合だ。
これらをまとめると,付加価値は
付加価値=純利益+金融費用+賃借料+減価償却費+人件費+税金
という要素で計算され,詳しくは図2のようになる。
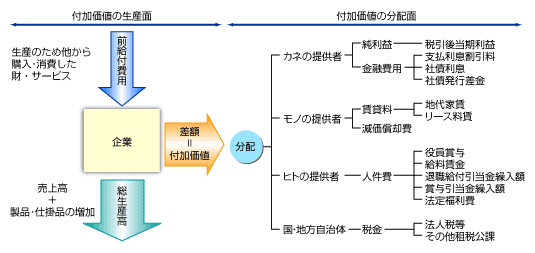 |
| 図2●付加価値の定義 |
定義通りは使いにくい
生産性の定義式は上記で説明した通りであるが,これをそのまま計算するのは大変だ。そもそも,すべての情報を収集するだけでも大変で,企業外部の者にとっては,すべての情報を入手できないことも少なくない。また,そこまで苦労して計算したところで,それに見合った多くのことが分かるわけでもない。
そこで,実務上は,もっと簡単に計算しても十分事足りる。また,分かりやすい指標を使った方が,むしろいろいろなこと(場合によってはショッキングなこと)が見えてくる。
まず,インプットである経営資源は,働く者にとって最も関係の深い従業員数としよう。これにより,いわゆる「1人当たり○○」が計算されるが,この数値は,職場で言われる「生産性を上げろ!」の「生産性」の感覚に最も近いはずだ。
アウトプットの候補としては,売上高,売上総利益,営業利益を使う。この3つは,どれを使うかによって意味が異なる。
3つの意味の違いを理解するためには,損益計算書は富の分配プロセスを表しているということを理解しよう。
図3を見ていただきたい。売上高は,まだ誰にも分配されていない富の源泉だ。これが順次,利害関係者たちに分配される。まず,売上原価で仕入業者に対して富が分配され,次の販売費及び一般管理費の人件費によって従業員に富が分配される。営業外費用の支払利息では債権者に富が分配され,法人税等によって国・地方自治体に富が分配される。最後に残った当期純利益が,株主に帰属する。
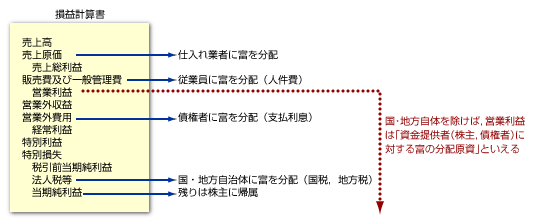 |
| 図3●損益計算書は富の分配プロセス |
ということは,営業利益は,その下で分配される債権者,国・地方自治体,そして株主に対する富の分配原資ということができる。国・地方自治体は少々特別な存在なので,これを無視して言えば,「営業利益は,資金提供者(株主,債権者)に対する富の分配原資」ということができる。営業利益がゼロ以下になるということは,株主と債権者に対して富を分配できないということなので,株式会社としての最低限の責務を果たせていない状態といえる。
3つの指標,それぞれの意味
損益計算書は富の分配プロセスということを踏まえて,まず,売上高を従業員数で割った,1人当たり売上高を考えよう。
売上高は,会社が稼ぎ出した富の総額であった。これを従業員数で割った1人当たり売上高は,会社という組織に属することによって,1人当たりが平均的に稼ぎ出した金額だ。この額は,「自分ひとりで稼ぎ出すのは無理」と思える額でなければならない。なぜなら,組織とは,人が複数集まって集団化することによってシナジー効果を生み出し,1人ではできない規模のアウトプットを出すことを意図しているからだ。すなわち1 + 1が2以上になるからこそ,集団化しているのである。ところが,1人当たり売上高が,自分1人でも稼げそうな額だとしたら,それは単に1 + 1が2にしかなっていないということである。これでは,わざわざ多くのストレスを抱えながら集団化している意味はない。
つまり,1人当たり売上高は,「その組織に属し続けるべきか否か」の指標といえる。もちろん,「自分1人でも稼げそうな額」をどう考えるかは人それぞれだ。その額が大きい人は,組織を離れていくし,そうでない人は,組織にしがみ続けることになるだろう。
次に,売上総利益は,付加価値にほぼ等しい。したがって,生産性の定義になるべく忠実に計算したい場合に,売上総利益を使う。ただし,製造業の場合は,売上原価に人件費が含まれているので,売上総利益をもって近似的に付加価値とみなすことが目的ならば,製造原価に含まれる人件費を売上総利益に足し戻す必要があることに注意が必要だ。
3番目の営業利益は,資金提供者に対する富の分配原資だ。これがゼロ以下になるということは,株式会社としての最低限の責務を果たせていない状態である。これを踏まえて考えると,1人当たり営業利益とは,「1人当たり,あとどれだけコストをかけたら,株式会社としての責務が果たせなくなるか」ということを意味しているということだ。つまり,「1人当たり追加的にかけられるコストの上限」だ。直接的な例で言えば,「年収の伸びしろの上限」と思えば分かりやすいだろう。
|





















































